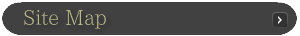【はじめに】
−インタビューにあたって
通常、俳優は多くの場合、特定の劇団や事務所に所属して仕事をしています。
しかし、平幹二朗さんは、舞台・映像などの仕事をする事務所に加え、個人で「幹の会」を結成し、株式会社リリックとの提携で「幹の会+リリック」として『王女メディア』や『オセロー』、『リア王』、『冬のライオン』など、自分が熱意を注ぐ優れた作品を、日本全国を小まめに回りながら演じて来ました。これは、現在の演劇界においては、「異例」のコラボレーションとも言えます。
まして、それが20年も続いたのは、稀な例としか言いようがありません。
なぜ、こういう形での公演が始まったのか。演劇プロデューサーで、このホームページの代表者でもある「リリック」の代表・秋山佐和子さんから見た「平幹二朗」という役者、そして平さんの人となりを語っていただきました。
秋山さんしか知ることのないエピソードも含め、皆さんがご存じのない「役者・平幹二朗」の姿がお伝えできれば幸いです。

−秋山さんと平さんの関係はどのように始まったのでしょうか?
最初はもちろん観客です。
私が初めて平さんの舞台を観たのは、高校生の時、越路吹雪さんと共演した1971年の『結婚物語 I do! I do!』(再演)というミュージカルでした。
生の舞台を見た第一印象は「えっ!テレビの原田甲斐とはまた全然違う魅力で素敵!舞台もなんて素晴らしい声なんだろう!」と思いました。
その時、平さんは38歳だったんですね。越路吹雪さんの年下の可愛くて若い旦那さんを演じていて、ステキでカッコいい旦那さんでした。
もしも年下の女優さんが相手役だったら、違う印象だったのかもしれません。
作品だけではなく、平さん自身が明るい印象でしたね。
芝居のことなんか何もわからない頃でしたけれど、前年の1970年に、NHKの大河ドラマで『樅ノ木は残った』が放送されて、その演技に魅せられていました。
このドラマで原田甲斐を演じた人が、ミュージカル I do! の 若い旦那さん役をどう演じるのか、観ないわけにはいかない、という感じでしたね。
−それが最初の観劇体験だったのですか?
いえ。
最初に舞台を観たのは、高校一年生の時に、学校の廊下に劇団四季の『さよならTYO!(とうきょう)』っていうミュージカルのポスターが貼ってあって、「観たい人は職員室へ」というので行ってみたら私一人だけで(笑)。
それが面白くて、劇団四季の芝居が観たいな、と思っていたら、次は『結婚物語 I do! I do!』だったんですよ。
同じ年に、劇団四季の座友になった平さんが、浅利慶太さんの演出で演じた『信長記』の舞台美術の凄さに目を奪われました。
私は、当時は美大を出て美術の仕事をしたい、と思っていたんです。
劇団四季の金森馨さん(1933~1980)の装置にショックを受けて、「舞台美術家になりたい!」と思ったのと、平さんとの出会いが同時期に重なったんですよ。
劇団四季を受けようと思った時は、もう研究所の試験が終わっていて、金森さんに「僕のところで一年間勉強して、来年劇団の研究所を受けなさい」って言われて、1979年に劇団四季の研究所へ入りました。
結局、金森さんに魅せられて、美大へは行きませんでした。
金森さんのアトリエで勉強している頃、三島由紀夫近代能楽集の『卒塔婆小町』で金森さんが「伊藤熹(きさく)朔賞」を受賞しました。
小町は平さん、演出は蜷川幸雄さん。
この三者のスクラムが見事な舞台で、私は大興奮しました。
平さんの小町も、もうそれはそれは絶品でしたね。
金森さんが頂いた賞の名前の伊藤熹朔(1899~1967)さんは、現代演劇の舞台美術に大きな功績を遺した方で、弟さんが俳優座の演出家・俳優だった千田是也(1904~1994)さん。
平さんが最初に出会った演出家なんです。
面白いご縁ですね。
金森さんの舞台美術は本当に素晴らしくて。
もっと長く生きていらして、私に才能があったら、舞台美術家になっていたと思います。
早世されてしまったことが、私の人生を変えたんです。
私が劇団四季の研究所に入所した頃は、もう平さんは四季を離れた後で、ちょうど帝国劇場で『近松心中物語』の初演をしていました。
四季の美術工房で小道具を創りながら、ラジオでその話を聴いていたのが昨日のことのようですね。
【平幹二朗との出会い】
−平さんとの「初仕事」はいつですか?
1995年、新神戸オリエンタル劇場での『オセロー』です。これが、「幹の会」としての第一回公演になるのですが、その頃、私は「幹の会」ではなく、新神戸オリエンタル劇場で制作の仕事をしていました。
劇場はダイエーの所有で、東京の事務所で、地方公演の勉強をするために、制作プロデューサーとして3年間在籍しました。
新神戸の劇場へも公演や打ち合わせでよく出かけていて、『オセロー』の取材が、平さんとの初対面でした。
その後、「阪神・淡路大震災」が起きて、『オセロー』の新神戸オリエンタル劇場での公演は中止になりました。
当時、私は劇場側の人間として、「幹の会」に対しお金を支払う立場で、東京にいたんです。
でも、平さんは、この震災の後、「みんなで神戸へ芝居をしに行こう。神戸の人たちを元気づけよう!」と声を掛けたんですね。
でも、神戸は芝居を観られるような状況ではなく、公演はできませんでした。
それで、当時、平さんのマネージャーだった方たちと、リュックとズックで廃墟になった神戸の街へ向かいました。
言ってみれば、「貰う方」と「払う方」と敵味方の関係ですから、長い時間をかけて神戸へたどり着くまで、一言も口を利きませんでした。
そんな中で、何とか事を納められ、多少なりとも「幹の会」にお支払いすることができました。
そんなことも経験し、一年後に劇場を辞めて、自分で「リリック」という会社を作ったんです。
「リリック」という言葉は、ギリシャ語で音楽の「詞」を意味するのですが、短い言葉で語感が良いのでこの名前にしたんです。
新しく演劇の企画製作の会社を作りましたので、よろしくお願いいたします、
というご挨拶状をお出ししたら、その翌日、平さんのマネージャーさんからお電話をいただいて、「『幹の会』と一緒にやりませんか」という、願ってもないお話をいただいて。それから20年なんです。
「阪神・淡路大震災」によって、幹の会と信頼を深めたスタートを切ることが出来たのだと思います。
−この時、平さんは62歳ですが、最初の「出会い」から実に26年後です。その時の印象は?
新神戸オリエンタル劇場にいた頃、『オセロー』の稽古を観に行ったんです。
稽古中に若い俳優さんたちに「君たち、酒を呑んでもいいけれど、ちゃんと芝居をやれよっ!」って平さんが怒鳴ったんですよ。
その後、幕切れ近くの場面で、ベッドの中に自害する短剣が入っていなくてはならないんですけど、何かの手違いで置かれていなくて。そうしたら平さんが物凄い勢いで舞台から降りて、通路際に座っている私の脇を、マントを翻しながらサーッと嵐のように去って行きました。
ロビーでスタッフに「稽古場がたるみ過ぎだ!」と怒っているのを聴いて、通り過ぎる時のマントの風圧と稽古場での厳しさに「あぁ、こういう人と仕事をするんだ」と改めて思いました。
あの風圧は今でも忘れられません。
−それを実現して来た秋山さんのバイタリティと行動力はすごいですね。
よく言われます(笑)。
自分で「やりたい」と思ったものは、時間を掛けてでも実現してしまいますね。
怖い物知らずなんでしょうか。
「やりたい」と思ったら物怖じしないんですが、できなかったことはたった一つ、「結婚」かな。
−それは「だった」にするのは早いでしょう。
そうですね。「僕はこの仕事に命を懸けてやってるんだよ。だから君も命を懸けて。」と言う平さんと一緒に芝居を創るのに、家庭を持っていたらできませんでしたね。
一つの物を目指している「運命共同体」のような感覚ですから。
ある時、倉本聰さんの『谷は眠っていた』を東京でやりたいと思ったんですよ。
これは、倉本さんが富良野へ移って「富良野塾」を始めて最初の作品です。
倉本さんの演出助手をやらせてもらった時代もあったので、親しくしていただいていたんですが、倉本さんは、この件はなかなか首を縦には振ってくださらなかったんです。
私も、二度ほど富良野へ伺ってOKが出るまでお願いして、ようやく「OK」をいただきました。
その時に倉本さんが、「俺が東京へ出て芝居をやるってことは、ブロードウェイの『オン』へ出るっていうことなんだよ」って。「これを失敗したら、俺は演出家としてもう立ち上がることはできないんだよ、それを分ってるのか」って言われたことがあるんです。
平さんの「命を懸けて!」というのも同じ意味だと思うんです。
一回でも失敗したら、もう次の試みはできなくなるから、そうならないように「命を懸けて」くれ、という。あぁ、一流の人は同じ事を言うんだなぁ、と思いました。
今考えると、倉本さんが東京で初めて演出家として仕事をする機会を私に託してくれたわけですが、平さんも、よく私に託してくださったなぁ、と思います。
−平さんの華やかさは天性のものだと感じましたか?
その才能を引き出したのは、俳優座の千田是也さん、劇団四季の浅利慶太さん、蜷川幸雄さん。
この三人の演出家と出会うということは、華やかな天性を多分に持っていたということだと思います。
その天性をご自分の努力によって開花させたのだと思います。
それには、幼少期の体験が大きいとも思うんです。
昭和8年生まれで、空襲に遭い、疎開もして、お母さまは被爆。
多くの同級生を亡くすという辛い体験もしています。
そうした辛い経験を経て、みんなの分まで自分がちゃんと生きて、仕事をしなくては、という強い想いがあったから、「俳優」という形で自分を究極まで表現する形になったんではないでしょうか? 戦争や災害のように自分の力ではどうにもならない事に対する気持ちが「演技」として爆発したのでは、と思います。
ご本人は、戦争はもちろん争い事は嫌いで、そういう感情が芝居に大きな影響を与えているんだと思うんですよね。
自分の身に降りかかった、どうにもならない不幸を、違う形でのエネルギーに変える力を持っていたんでしょうね。
その分、大きな「痛み」も心の中に抱えていたと思います。
平さんの演じる悲劇は、高みから下へ転げ落ちる落差の激しさ、急こう配。
そして、その速度に魅力があると思います。
辛い体験を自身の糧にして表現できるからこそ、観客は最高のカタルシスを味わえたのではないでしょうか。
もう一つ、お母さまの存在が大きかったと思います。
お母さまをご存じの方は皆さんそうおっしゃいますね。
大人になって、仕事を始めても、平さんの食事を作って待っていたそうですし、公演のご案内も劇場でのお客様の応対もお母さまがされていらっしゃいました。
掲載記事のスクラップも全部キチンとされていたと平さんから聞いています。
そういうキチンとしたところは平さんにも受け継がれていました。
お父さまを早くに亡くされ、「平幹二朗という役者は、母と二人で創り上げたものです」とおっしゃっていました。
被爆されて健康を害しながらも、一生懸命に尽くしてくれたお母さまへの想いは強かったと思います。
秋元松代さんの『元禄港歌』や、『王女メディア』のような母と子の物語には、とても興味を持ち、意欲的でしたね。
こういう環境や生い立ちだったからこそ、他の人にはないものがあり、「追求したい」という熱心さは半端ではなかったことにつながったのでしょう。
同じ作品を繰り返し上演したのもその現われでした。
「年代によって同じ役でも気持ちが変わるから、またやってみたいんだよ」とおっしゃってました。
【「幹の会」での仕事】
−「幹の会」以前と以降、という分け方で、舞台年譜を拝見すると、出演する作品の傾向が変わりましたね。
「幹の会」ができる前に、シェイクスピア・シリーズとして1992年から3年の間に、『テンペスト』、『リチャード三世』、『ヴェニスの商人』などを上演しましたけれど、東京での拠点にしていた新大久保の東京グローブ座の経営が変わるなど、外的な要因もあって、当初の目的だった「全作品の上演」の方向も変わりました。
そんな経緯もたどり、「幹の会」を立ち上げて、本当に上演したい作品だけをコツコツやって行こう、ということになったんです。
−「幹の会」の結成が起爆剤になったのでしょうか、1995年近辺は舞台の数も多いですね。
『オセロー』を「幹の会」でやって、立て続けに『リチャード三世』、『四谷怪談』、96年が「幹の会」の『メジャーフォーメジャー』、『夢幻にて候』、新派で『明治の雪』、『女優』ですね。
「幹の会」が起爆剤になって、役者として乗りに乗った60代を迎えたんじゃないでしょうか。
もう立派な役者さんになっていた年代ですね。大劇場だけではなく、ライフワークとして演劇鑑賞会で地方を回ろうというのは、俳優座での若い頃の経験や、劇団四季での地方公演などの下地があったのと、ご自身がそういう芝居のやり方が好きだったんでしょうね。
新劇系統の奥深い作品を何度も上演して掘り下げていく、という形が。
−『王女メディア』の千秋楽に「やっと初日が出た」ということも、その延長線上にあったわけですね。
そうですね。「あっ、これをやりたかったんだ、そして続けて行きたかったんだ」と思いました。
続けてあげたかったと思います。あそこまでやり続けて「初日が出た」という感覚は凄いものです。
追い求めるエネルギーとパワー、そして繊細さ。『王女メディア』は、蜷川さんの演出で上演した1978年から考えれば38年間、自分の身体の中に棲みついていたわけですから、まだまだ上演したかったでしょうね。
−平さんと喧嘩したことは?
怒られたことはたくさんありましたけれど、喧嘩はないですね。喧嘩したら続いていません。
お互いにお互いを必要だったんでしょうね。(笑)
怒られたことも大きなことでは殆どありません。
日常のことばかりですね。
旅公演のある日の夕食が、ホテルに入っているチェーン店の居酒屋だったんです。
夜中に平さんから東京の私の家に電話があり、「すごくまずい飯だったよ。
二日前のご飯と昨日のみそ汁、甘ーいアジのミリン干し、これだけ。
半分の役者が他の店へ出て行ったけど、僕が出るわけには行かないから、残ってくれた役者に追加で焼鳥を振る舞ったんだよ」って。
その時点では平さんは酔っていますから、壊れたテープレコーダーのように「二日前のご飯と昨日のみそ汁、甘ーいアジのミリン干し」と一時間も繰り返したんです。
私は「申し訳ありません」「おっしゃる通りです」「以後気を付けます」の三つの言葉を繰り返すしかありませんでした。
「君はいないしさ。僕一人だったんだよ」と平さんが悲しそうに言った時、私は心から可哀想なことをしてしまったと思って、「すみませんでした」と言ったら、「じゃあね」と言って平さんは電話を切りました。平さんは、相手が何を言った時に、本心からなのか口先だけなのか、分かっているんですね。
だから、私が「本当に申し訳ない」と思ったのを感じた瞬間に、怒りが鎮まったんです。
―では、嬉しかったことは?
他人には相談できない事を「これ、どう思う?」と相談してくださった時ですね。
「信頼してくれてるんだな」と感じました。
どの世界でもなかなか口には出せないことがありますが、そんなことも相談してくれたのが嬉しかったですね。
平さんが持っている「努力する」「嘘をつかない」「お金にきれい」という天性のものを、私も持っている事を、どこかで「同じ匂い」というような感覚で感じ取ってくださっていたのではないかと思います。
それから、役者として一流の人は人柄も一流、ということを平さんとのお付き合いの中で学び、感じられたのも財産です。
何をもって「一流」とするのかは難しいですけれど、一つ例を挙げれば、平さんほど有名でも、誰にでも分け隔てなく接していました。
地方へ公演に出かけて、楽屋へいろいろな方がご挨拶に見えた時に、メイク中でも手を止めて、自分から立ち上がって楽屋の入り口まで来ていました。
終演後、楽屋口で待っていてくださるファンの方々にも、とても丁寧でしたね。こういうところにも人間の「品格」が出るんだと私は思うんです。
もう一つは、相手を尊重してくれることです。
自分が好きな芝居ができるのは、観てくれるお客様がいて、それを公演する場所があり、準備をしてくださる方々がいてこそ成り立っていることを、よくわかっていましたね。
人を見る眼も厳しかったですけれど、自分を見る眼が一番厳しかったですね。
そういう人に尊重してもらえる、というのは嬉しいことです。
−役者は良い意味で「曲者」の方が魅力的だと思いますが、平さんの「曲者」ぶりは?
曲者、とは言えませんね。
名優でありながら世間一般の「普通の感覚」をも合わせ持っていました。
人としての品格もあったし、貪欲さもあったけれど、自分を客観視して、律することができたのは、人間としても一流の証だと思います。
役者である前に、一人の人間であること、それが備わっていて、まさに「実るほど頭を垂れる稲穂かな」というところはありました。
ご自分の芝居が巧いとは決しておっしゃいませんでした。
考えていることの次元が違うんですよね。
常に前を見ている、ワクワクすることを探している、新しいことへ挑戦する感覚がすごく若かったですね。
私は20年間ついていくのに必死でした。油断していると、遙か先の方を歩いている。
私はいつも小走りでした。
外国の名優が、エレベーターに乗っている時に哲学者に見えたという話を聞いたことがありますが、亡くなった年に「松尾芸能賞」の大賞を受賞されたパーティの時の姿に、まさに「哲学者のような」感覚を持ちました。
そういう部分が尊敬できたから、20年間ご一緒できたんだと思うんですよ。60年の俳優人生の三分の一に当たるわけですから。
−その中で一番印象に残っているものは、やはり『王女メディア』ですか。
そうですね。
「幹の会」では2012年が初演、2016年が再演になりますが、初演の時は高瀬久男(1957~2015)さんに演出をお願いしました。
平さんも高瀬さんの文学座での仕事ぶりを評価していました。
高瀬さんの演出は「リアル」に追求するスタイルで、平さんも試行錯誤を繰り返しながら演じていましたね。
再演の時は、メディアの女性としての感情が爆発する部分をどう表現するか、さらに練り上げ工夫して、という予定でした。
ところが、高瀬さんが亡くなってしまい、田尾下哲さんに高瀬さんの志を引き継いだ演出をお願いしました。
3月6日、水戸の千秋楽で、思い切って今まで、まだどこかで様式に頼っていたのを止めて、生身の女性として演じたら、芝居がトントンと運んで「やっと初日が開いたよ」と喜んでいました。
だからこそ、次もやりたかっただろうな、と思います。
水戸では2日間の公演で、前の日の舞台とは全く違うメディアには私も驚きましたし、「あぁ、これが平さんが目指したメディアだったんだ」と感じ、終わってすぐに楽屋へ飛んで行ったら、平さんが一人スッキリした顔で嬉しそうにニコニコしていましたね。
−平さんは「幹の会」で演出家として携わっている作品もありますが、「演出家・平幹二朗」というのは?
作品に対するイメージやテーマが、音楽や衣裳など、随所に現われていましたが、「イメージ」をとても大事にしていましたね。
スタッフとの打ち合わせを綿密に重ねて、自分のイメージをどう具体化するか、という。
それから、「本読み」(稽古の最初の段階)には非常にこだわりがありました。
「本読みまでには自分の台詞は覚えて来てください」というのが第一方針。
もちろん、ご自身の台詞が一番多いわけですけれど、全部覚えて来るんですよ。
だから、覚えて来なかった人は肩身が狭いんです(笑)。
テーブルでの本読みに一週間以上かける丁寧な稽古で、気持ちの移り変わりを台本に記して、一言ずつチェックをして、役ごとに発表するんです。
これは劇団四季で浅利さんがやっていた演出法で、四季で受けた影響が大きかったんでしょうね。
その段階で、みんなが共通認識を持って「立ち稽古」に移る、という方法でした。この作業をキチンとしていたから、平さん独特の「朗誦術」が生まれたんでしょうね。
「立ち稽古」では、他の役も演じて見せるんですが、これが上手なんですよ。
今は、こんなに丁寧な稽古をする舞台はあまりないんじゃないんでしょうか。
平さんの稽古は、まず役の心情を造ること、それから台詞を活かす、という順序でした。この形で2001年と2005年の『冬物語』、2002年の『リア王』、2004年の『オイディプス王』、2006年の『オセロー』と4本、公演としては5公演の演出をして、「もう疲れちゃったよ」って。
演出しながら、自分も芝居をしなくてはならないわけですから。
普通は演出家はそれに専念していればいいわけですが、役者が演出を兼ねる場合はそうは行きません。
時には、自分の中で演出家と役者の考えが相反することもあるわけじゃないですか。
演出家は孤独な作業である一方、座長として全体をまとめなくてはならないし。
演出をすることで、役者としての自分に遠慮をしなきゃならない場合もあるし、役者として納得がいかない演技になってしまいます。
「オセロー」が終わった時、「僕は役者一本でやっていきたい」とおっしゃいました。
平さんが演出した『オセロー』の時にはフラメンコ、『オイディプス王』の時にはゴスペルを、出演者全員で習いに行きました。
役者は芸の助けになることを身に付けるべきだ、という考え方なんです。
公演が終わると辞めてしまう人が多い中、レッスンを続けていたのは平さんだけでした。
『オセロー』では息子の岳大君のイアーゴーがフラメンコのステップを踏む場面を見せ場の一つにしました。
彼は今も続けていますね。
10年継続して、素晴らしい上達です。努力して追求する才能も親譲りなのかな。
平さんは、演出をする時でさえも、吸収したいんですね。役者兼演出家の特徴かもしれません。
「演歌」も習ったんですよ。
石原裕次郎の曲を習ったりして、ミュージカルをやりたい、という気持ちもあったみたいです。
「またI do!をやりたい」なんておっしゃっていた時もありました。
演出家としても役者としても、「表現」に対する貪欲さは共通していましたね。
だからこその名優だったし、常に何か「面白いこと、新しいこと」を探している感覚の若さやしなやかさを失わなかったですね。
いろいろなことに興味津々で、「何でもやってみたい」っていう。
平さんが声楽やカラオケのレッスンを本格的に受ける理由は「役者」以外には見当たらないでしょう。
仕事を一緒にやり始めた頃、電話を切る時のコミュニケーションをとるための挨拶は「面白い事あったら教えてね」でしたね。
−「仮定」としての質問が残念ですが、平さんがお元気だったら、次は何をやろうと…。
『王女メディア』しかないですね。
韓国での上演も視野には入れていましたし、国内でまだ伺っていない場所もありました。
また、「素晴らしかったからもう一度」というお声を頂いているところもあります。
そういうところでの上演は可能かな、とは思っていました。
「幹の会+リリック」は、「絶対に赤字を出さない」という方針でやっていましたから、もし平さんがやりたい作品があっても、それが興行として成り立たなければ即座に「やめよう」という潔さがありましたね。
舞台の質を上げるためにはお金をかければできてしまう部分もありますが、平さんは、全部予算内で納めてこそ、という終始一貫した姿勢でした。
赤字を作ったら続けることができませんから。
そこをクリアした上で「何をやるか」を考える点では、プロデューサーとしては助かりましたね。
予算を気にして、稽古場で「帽子を一つ買ってもいいかなぁ」なんて聞いてくるんです。
でも、自分が演出する時は「車を一台出せないかな」なんて(笑)。もちろん、無理なんですが、「夢」の部分だったんでしょうね。
ただ、名優でありながらキチンと世間のルールや人間としての常識を大事にしてくださったから、20年間のお付き合いができたんでしょうね。
その役者人生の最後に、自分と一体だったとも言える『王女メディア』を演じ切り、共に消えてしまった、という感じですね。
半年以上を掛けて50か所以上の会場を回って100公演の芝居をする、という旅公演を毎年のように続けてやっていましたが、「時間を空けてしまうともう一度ネジを巻き直すのが大変なんだ」と。
もちろん、大きな舞台での大仕掛けの芝居もお嫌いではなかったでしょうが、数百人単位の公演で、毎回違う場所へ自分の芝居を持って行くことの意義と喜びを感じていたのでしょうね。
「土地によって会場も会員さんの気風も違う演劇鑑賞会の旅公演で毎回100公演の芝居を続けていなかったら、ここまで芝居が上手くはならなかったよ」と鑑賞会にいつも感謝していました。
こんな話をしても仕方がないのはわかっていますが、もしも、『王女メディア』の先の公演予定が決まっていたら、亡くならなかったんじゃないか、って今でも思っています。
−このホームページには、20年を「運命共同体」として一緒に過ごした秋山さんの想いが詰まっているんですね。
はい。
ただ、それは私だけではなくて、メッセージをお寄せいただいた方々や、各地で平さんの舞台に共感・感動してくださった皆さんへのお礼の意味もあります。
ある方に言われたのですが、「存命で活動中の役者さんのホームページならよくありますが、亡くなった役者さんに関するものをこれから作る、というのは珍しいですね」って。
でも、このホームページには、平さんに関わった方々をはじめ、多くの方の「想い」が詰まっていると思うんです。
その想いを分かち合っていきたい、まだまだいろいろなお声をいただきたい、という気持ちで始めました。
平さんは年を重ねるごとに増えてゆく苦労を克服する努力を嫌だ、とは思わずに、楽しんでいました。だからこそ、「天職なんだよ」という言葉が出たんでしょうね。もちろん、辛いこともたくさんあったでしょうけれど、
平さんは辛いことや苦しいことを楽しみに変える天才ですね。だから、自然に乗り越えられるんですね。
以前は「実力のある役者に出演して貰いたい」
とおっしゃっていましたが、最近は「努力する人たちと一緒に作りたい」と考え方が変わりました。
「下手でも努力する人は進化があるから面白いんだよ」って。
名優であったことは間違いありませんが、「人生の達人」でもあったんだなぁ、と。
自分の力ではどうにもならない「運命」を受け入れて、それに立ち向かって行くことが平さんを強くしたんでしょうね。
「逃げ場」もなかったでしょうし、「逃げる」という発想もなかったんじゃないでしょうか。いろいろ失敗もあったでしょうけれど、それは誰にでもありますし。
繰り返しになりますが、そんな「希代の名優」と言える方と20年も歩みを共にできた、そして、一生懸命に作った作品が各地の皆さんに喜んでいただけた、というのが、プロデューサーとしての最大の喜びです。芝居の仕事をしていて良かったな、と思います。
欲を言えば切りがないですが、もう一度、平さんと「王女メディア」の公演がやりたかったですね。
−長時間にわたり、ありがとうございました。