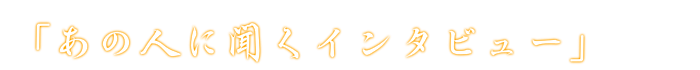
聞き手:中村 義裕(演劇評論家)
【第二回】
三田 和代さん(女優)
このコーナーは、平さんとゆかりの深かった方々に、さまざまな想い出をお話いただくコーナーです。
第二回のゲストは、女優の三田和代さん。今年、女優デビュー51年目を迎えた名女優に、芝居の世界のあれこれや、平さんとの思い出を語っていただきました。

−まず、三田さんご自身の「歩み」について伺いたいのですが、女優を志したきっかけはどういうものだったのでしょうか。
三田:小学生の頃から芝居が好きだったんです。私は大阪出身、友達と脚本を書いて、学芸会で芝居をやっていました。だから、何の抵抗もなく芝居の道へ進みました。その頃は、まだミュージカルが少なく、いわゆる「新劇」が盛んで、「ことばの演劇」をやりたい一心でしたね。当時は「三大劇団」と言われた文学座、劇団民藝、俳優座が全盛の時代で、私は上演する芝居がお洒落な、文学座が一番好きだったんです。ただ、文学座に研究所があるのを知らず、俳優座に養成所がある、という声しか大阪には聞こえて来なかったんです。それで、俳優座の附属俳優養成所を受けて演劇研究所に入りました。
その養成所で平さんは5期生、私は15期生で、丸10年違うんです。当時は、10年違うと「大先輩」で、平さんに対しては「先輩」という意識が強くて、背中ばかり見ていた感覚がありますね。俳優座の養成所を卒業して、やはり一番好きだった文学座の研究所へ行きたくて、試験を受けて入りました。俳優座で研究生を終えていましたので、文学座で一年やれば準座員になれるかもということでしたし。
ところが、1966年に日生劇場の制作で上演された『アンドロマック』(作:ラシーヌ)で、出演予定の渡辺美佐子さんがご病気で出られなくなってしまって、文学座を受ける時に同時に受験していた劇団四季の浅利慶太さんが私のことを覚えていたんです。「結局、四季へは来なかったけど、あの子はどこへ行った」ということになり、浜畑賢吉さんが私を探して、出演するように説得されました。『アンドロマック』はこの時が再演で、日下武史さん、市原悦子さん、平幹二朗さん、渡辺美佐子さんという中堅の俳優さんで上演しました。その一角の渡辺さんが抜けることになって、急きょ「新人でやろう」ということだったようです。私はまだ文学座の研究生でしたから、その立場では出演できませんので、文学座を辞めてフリーとして出演しました。
この舞台で、平さんと初めての共演で、私の役は平さんを好きになる役でした。ところが、一回も顔を合わせずに、「好きだ、好きだ」と言っているだけの不思議な芝居なんです。主な登場人物四人がみんなそういう構成になっていて、一度も会いませんでした。「会う」というのは、舞台でお互いのやり取りがない、という意味で、稽古場などではお目にかかってますけれど。この公演がきっかけで、1966年の7月に、四季に入団し、それから17年在籍しました。
−私が三田さんの舞台を最初に拝見したのは、渋谷のパルコ劇場がまだ西武劇場といっていた頃に上演された劇団四季の『汚れた手』で、ちょうど40年前になります。三田さんが四季におられた時期ですね。
三田:古いですね! 去年が女優としてスタートして50年だったんですよ。女優としてお金をいただいた最初の仕事が舞台で、今年で51年目に入りました。役者って、年を取ったらいろいろな経験で楽になるのかと思ったら逆で、どんどんできないことが増えて、しんどくなるんです(笑)。台詞もだんだん覚えられなくなってきて、「あぁ、とうとうこのエリアに入ったか」と思っています(笑)
私は、芝居の間は相手役や恋人役を好きになっちゃって、終わってもしばらくは余韻が残っていて、忘れられないんですよ。昔、恋人に「お前は芝居が終わって身体が帰って来ても、心が戻ってこないんだな」って言われたことがあります。役者ってそういうものなんですね。
−俳優座の養成所、劇団四季、フリーという俳優としての歩みの中で、幅広いジャンルの作品を拝見しました。海外の作品で言えばユージン・オニールの『喪服の似合うエレクトラ』や、『ハムレット』のガートルード、あるいは商業演劇の分野では杉村春子さんと山田五十鈴さんが共演した『流れる』、また、博品館劇場での朗読劇『イブラヒムおじさんとコーランの花たち』…。その幅の広さに驚きますが、共通して感じたのは、三田さんの透明感のある、薄いガラス板を震わせるような「声」でした。
劇団四季は台詞の朗誦に独特の方式を持っていますが、その影響でしょうか。
三田:劇団四季で芝居を勉強した人は、みんな母音に重点を置いた独特の発声法を仕込まれますが、私がいた頃は、浅利慶太さんが母音に重きを置いた発声法を提唱し始めた頃で、まだ今のように定着はしていなかったんです。当時、平さんは「団友」という立場で、「劇団のお友達」として出演されていましたね。当時はラシーヌやジロドゥのような、一人の役者が長い台詞を朗誦する芝居が多かったんです。台詞を大事にする芝居がやりたくて四季に入りましたから、そういう作品に魅力を感じましたが、自分では「声」を意識することはありませんでした。台詞がキチンとお客様に届くように言おうとは考えます。ただ、まずは役の人物をどう創るかですね。役の気持ちがわからないと、声がきちんと出ないんですよ。
私の声は高くなくて中音域だったんですが、四季の頃は高い声を要求されましたね。フリーになってからは、役の気持ちが表現できれば、その音の高い、低いは考えなくなりましたね。
−舞台の数も大変な多さですね。お願いする側が信頼感を持っているゆえでしょうが、役の幅を広げられた秘訣はあるのでしょうか。
三田:四季での経験を経て、フリーになった時、40歳でした。四季に在籍中の1985年に、東宝公演の『にごり江』で演出家の蜷川幸雄さんから声を掛けていただいて、それをバネにして飛び出して、何でもやりたい、という気持ちでした。新鮮でしたし、フリーになってからはいろいろな方と出会い、ディスカッションしながら芝居を創れることが嬉しかったですね。
そういう点でも、外の世界を見せてくれた蜷川さんとの出会いは大きかったですね。蜷川さんは役者の発想を活かす工夫をしてくれる演出家でしたから、演出家や相手役とのディスカッションの楽しさを教えていただきました。
井上ひさしさんとの出会いも私には大きかったですね。「日本のことば」を書く劇作家としての魅力は素晴らしいものでした。ただ、本が遅いので有名でしたから、寿命をずいぶん差し上げたんじゃないでしょうか(笑)。『小林一茶』、『藪原検校』なんかは好きな芝居で、10本以上は出ているんじゃないでしょうか。
商業演劇も良き時代で、山田五十鈴さん、森光子さんなどが大きな輝きを放っている時代に、脇役での出演でも、刺激を受けて勉強になりましたね。
−平さんとは、舞台の次はテレビでの共演でしたね。
三田:はい。1970年のNHKの『樅ノ木は残った』でまたご一緒しました。今度は夫婦で正妻の役なのに、また一度も面と向かって芝居をしていないんです。結婚する場面ぐらいは一緒だったのでしょうけれど、私は白無垢を着ていたので見えませんでした。平さんの原田甲斐は、結婚してすぐによそへ女性を作ってしまう役でしたから、正妻の私は取り残されちゃって(笑)。だから、この時も背中しか見ていないんです。
−その後、かなりの時間を経て、2006年に「幹の会」の『オセロー』で平さんと、今度は顔を合わせて夫婦役での共演、が実現しました。
三田:平さんとちゃんと心を開いて話せるようになったのは、『オセロー』からじゃないでしょうか。平さんが70代、私が60代。それまでの間は、相手役としてご一緒した回数も少ないですし。ずーっと背中を見て来た先輩と、ようやくフラットな感覚で話ができるようになった感じでしたね。
デズデモーナは難しかったですね。とても孤独な人だったんだな、と思いました。人を愛しすぎてしまうと、「満ち足りてハッピー♪」という状態を超えて、孤独になってしまうのだと思うんですよ。だから、あの役は一人で子守り歌を囁くように歌ってしまうんじゃないかな。どこか、翳りがあるような女性ですね。この感触は、平さんが、ムーア人であることのコンプレックスをオセロー役の解釈の根底においていらしたので、そんな風に感じたのかもしれません。
−平さんのオセローはいかがでしたか。
三田:年の離れた奥さんをもらってしまったという感じでしたね。それが疑心暗鬼のもとになるのですが、威張っていなくて、いつも相手を気遣ってしまう。それがなければ、もっと幸せな夫婦でいられたのかもしれないのに、お互いに図太さがなくて招いた悲劇だったのかもしれません。それでいて、お互いが「孤独」を抱えているような。
芝居は、相手役の芝居を受けてするわけですから、平さんが持っている空洞や虚無感のようなものが伝わって来たのかもしれません。平さんご自身はすごく温かいものをお持ちなんですけれど、それが薄いベールをかぶっているような。それが、『オセロー』の後、2014年にシアターコクーンで上演した『炎立つ』(ルビ;ほむらたつ)の時には、最後のベールもなくなっていた感じでした。平さんは80歳になろうというところですね。
いろいろな俳優さんとご一緒しましたけれど、あの距離感は平さん独特のものかもしれません。もうそれがほとんどなくなった頃だったからこそ、もう一本一緒に芝居をしたかったのに、すっと逝かれてしまって。ここまで親しくなれて、これからもう一本創れたら、どんなものができただろう、と思ったらすごくショックで、亡くなったことを知ってからの数日間は喪失感が大きくて口がきけませんでしたね。あまりにも急でしたので。
−俳優座時代から劇団四季を経てフリーという役者の歩みの中で、時々の距離感はあったのでしょうが、言わず語らずにわかるような何かがあったのかもしれませんね。それが、『オセロー』で開放されたような。
三田:そうかもしれません。同じ匂いを感じる珍しい間柄なのでしょうか。役者として歩んで来た氏素性も似ていますし、二人だけに共通するような会話があったような気がします。浅利慶太さん、蜷川幸雄さんという演出家をそれぞれのフィルターで通り、シェイクスピアの作品も演じ、「言葉、ことば」で歩いて来た道が、似ているという意味では「妹分」みたいに感じられていたのでしょうね。
『炎立つ』の稽古場でもそんなことがありました。会話の中身は、美味しいお店を見つけたとかそんな話で、難しい芸術論を闘わせるわけではないんです。平さんって、こんなに楽しい方だったんだ、って、稽古場へ通うのが楽しかったですね。
―平さんとの印象的なエピソードがあるそうですが。
三田:そう言えば、一度だけ手紙をもらったことがありました。2004年に新国立劇場で『喪服の似合うエレクトラ』に出ていた時に、旅公演の途中でフラッと平さんが舞台を観に来られて、手紙付きのお土産をいただいたことがあるんです。そのお土産が、新幹線の駅の売店で買ったようなお漬物で、平さんのイメージには似合わないんです(笑)。
この作品は、ギリシャ悲劇のソポクレスの『エレクトラ』をもとにユージン・オニールが書いたもので、その時、私は『エレクトラ』ではクリュタイムネストルに当たるクリスティンという役を演じていたんですが、平さんからの手紙に、「嫉妬を持って観てました。女優として」って書いてあったんです。私は、素敵な褒め言葉だと感じたのと同時に、平さんの中のある感覚を刺激したんだな、という意味でも嬉しかったですね。
−よくわかりますね。三田さんの演技を目の当たりにしたことが、『王女メディア』の演技にも現われていたのかもしれません。
三田:その手紙が平さんなりの正直な表現だったんでしょうね。そういうことを考えると、いろいろな物を解き放たれて、自由な感覚で芝居をされている平さんともう一本、一緒に芝居をしたかったと心底思います。
−もし「次」があったとしたら、どんな作品になったのでしょうね。
三田:やはりシェイクスピアみたいな台詞劇でしょうか。コメディも面白かったかもしれません。お互いに、「こういう球を投げるよ」というボールの投げ合いをするような喜劇がやりたかったですね。
こうやって思い返しながら話してみると、平さんっていろいろな姿が見える面白い方だったんですね。非常に抽象的な方だと感じていたのですが。とても魅力的な方だったとつくづく思います。
こうして亡くなった後も平さんを偲ぶ方々が大勢いらして、ホームページが残っていくのは嬉しいことですね。
―ありがとうございます。こうして平さんと縁の深い方々からのお話を伺えるのは喜びです。三田さんは、さらにご活躍をいただけると思うのですが、今後のご予定は?
三田:7月5日に新宿の紀伊国屋サザンシアターTAKASHIMAYAで初日を開ける井上ひさし作『イヌの仇討』の稽古が6月に始まります。29年ぶりの再演で、台詞劇でほとんど動きがないんですよ。「赤穂事件は仇討ちではなかった」という話で、大石内蔵助は出て来ないんです。これが終わった後、10月5日が初日で、新国立劇場でジロドゥの『トロイ戦争は起こらない』を栗山民也さんの演出でやります。
−お忙しい日々が続きそうですが、頑張ってくださいね。楽しみに拝見に伺います。今日はありがとうございました。

三田 和代:プロフィール
大阪府出身。俳優座養成所を経て、1966年、日生劇場制作『アンドロマック』で舞台デビュー。以後、劇団四季を経てフリーに。以後、ユージン・オニール作の『夜への長い旅路』、『喪服の似合うエレクトラ』、テネシー・ウィリアムズ作『地獄のオルフェウス』、チェーホフ作『かもめ』などの海外の名作に多数出演、2006年には『オセロー』で平幹二朗と共演、デズデモーナを演じる。日本の作品では、井上ひさし作品への出演が特に多く、『國語元年』、『雨』、『小林一茶』、『紙屋町さくらホテル』、『頭痛肩こり樋口一葉』、『夢の裂け目』など、その確かな台詞術と高い演技力が評価されている。
これらの演技に対し1986年に第21回紀伊國屋演劇賞、1994年、第45回芸術選奨文部科学大臣賞、1997年には第5回、2000年には第8回読売演劇大賞最優秀女優賞など、受賞多数。2004年、紫綬褒章を、2015年、旭日小綬章を受章

芝居の話が止まらない二人

今日のインタビューは3時間に及んだ

2016年に芸能生活50周年を記念してユニバーサルミュージックより雅楽師東儀秀樹と三田和代による百人一首の朗読と音楽を融合させた「花の色は・・・〜百人一首に詠われた日本の四季、日本の心〜」CDが発売された。

「イヌの仇討」チラシ表

「イヌの仇討」チラシ裏




