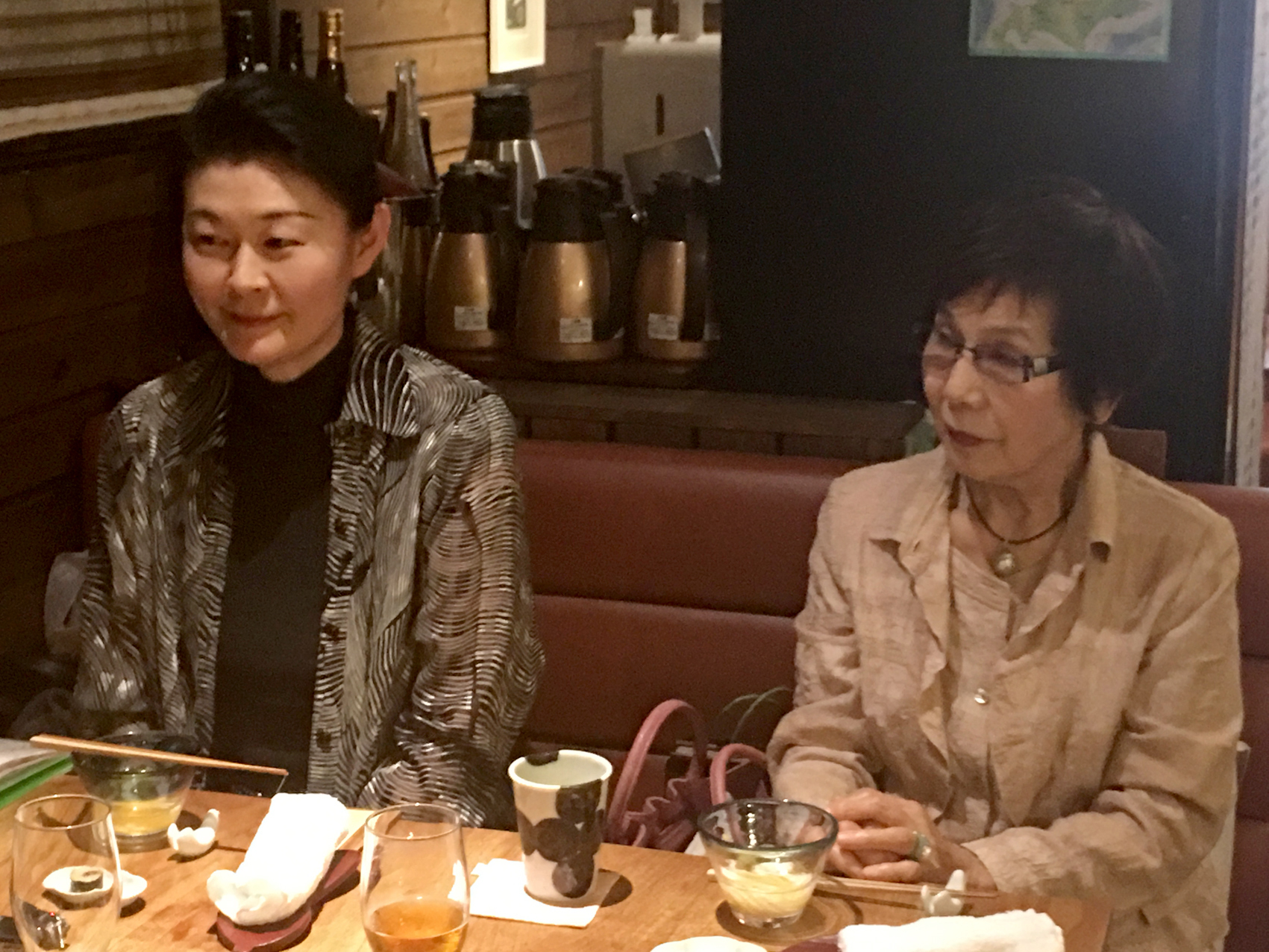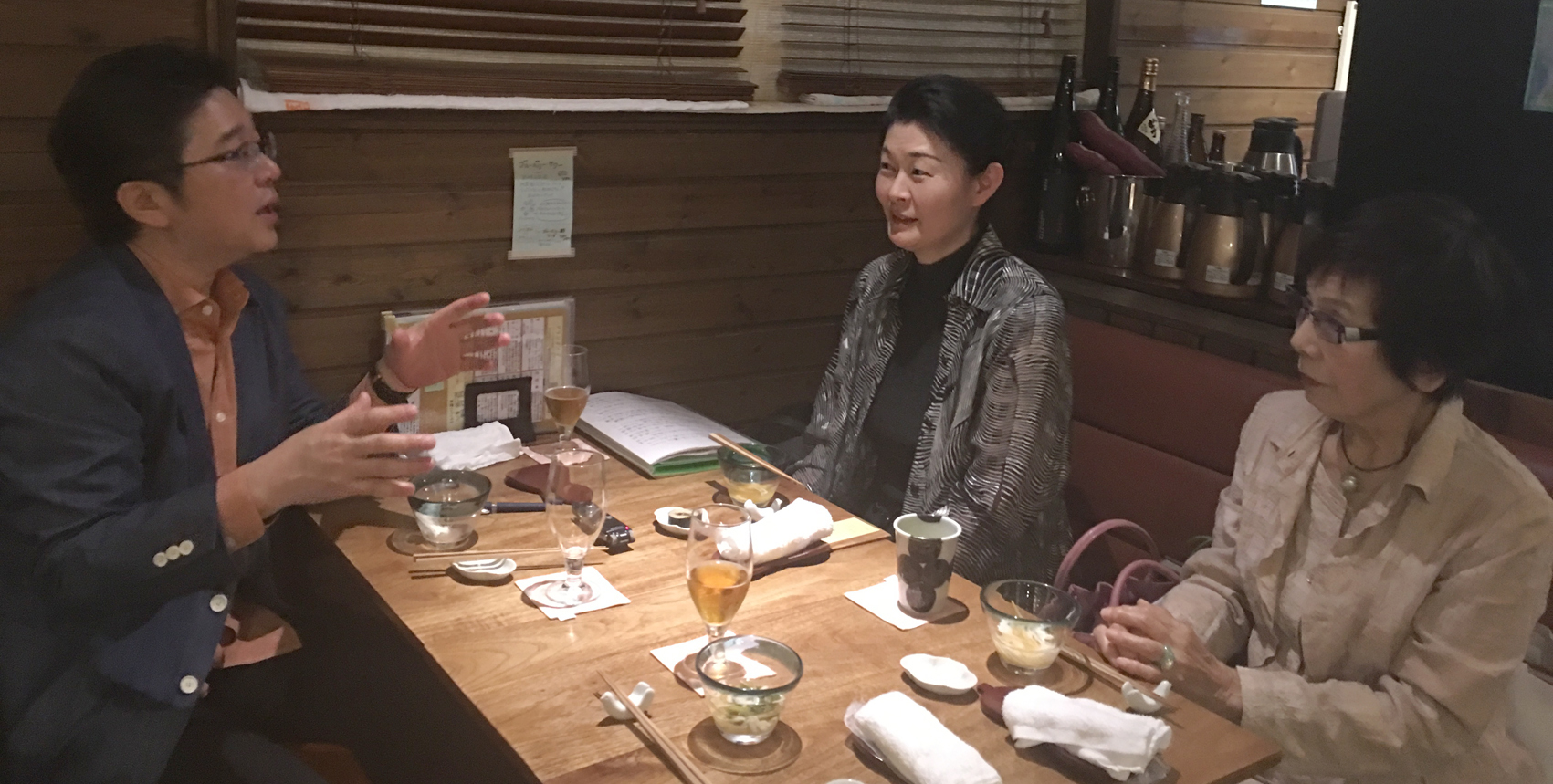聞き手:中村 義裕(演劇評論家)
第十回「『平さんまみれ』お二人」
福田フジ子さん 土谷治子さん(幹の会会員)
このコーナーは、平さんとゆかりの深かった方々に、さまざまな想い出をお話いただくコーナーです。

−今回は、趣を変え、「平さんまみれ」とも言える熱烈なファンの方お二人、福田さんと土谷さんにお話を伺いました。年齢も経歴も違う二人の女性が、「平幹二朗」の舞台の魔力に惹かれ、心を開いて話ができる「友人」として、今もお付き合いが続いています。
平さんが歿して一年半、天国の平さんは、今も変わらぬ想いを持ち続けるお二人を微笑みながら見ているでしょう。役者にとって、ファンの方は多ければ多いほどありがたいものです。「深く」「浅く」、ファンの方々の色合いもさまざまですが、「自分をずっと観てくれている」ファンの存在は大きな励みになります。
福田:私は、今日は函館から来ましたが、昨夜は緊張して眠れませんでした。毎年、平さんの舞台に合わせてスケジュールを組んで、その時に東京へ来て、クラシックのコンサートや他の芝居、シャンソンや落語などを楽しんで帰ります。その間に、平さんの芝居は二回観るようにしていました。
『百人の舞台俳優』(昭和44年発行)という、劇評家の戸板康二さんがお書きになった本に平さんは『アンチゴーヌ』のクレオンの役で取り上げられているんです。この本に書かれた時、平さんは35歳なんですよね。
雑誌のインタビューや特集などはたくさんありますが、平さんだけのことを書いた本がないのは残念ですね。ぜひ拝読したかったです。
−この『百人の舞台俳優』という本は、その当時の名優、平さんがおられた俳優座で言えば千田是也、東野英治郎、小沢栄太郎、東山千栄子、他にも文学座の杉村春子、劇団民藝の瀧澤修、宇野重吉、細川ちか子、歌舞伎の当時の名優たちなど、綺羅星のごときメンバーが並んでいます。今も現役でご活躍の方は少なくなってしまいました。
本は、記録は残せますが、最後は観客の皆さんの心の中の宝箱にあるのでしょうね。
平さんは、「蓮の花は泥沼の上で咲くのを見せる仕事であり、泥沼の中を見せるものではない」という、一種の美学をお持ちでしたからね。
福田:ご自分の活動や自叙伝のようなものを本にまとめて残さずに、お芝居一筋だったのはいっそ清々しいな、と思いもします。ただ、こうしていなくなってしまわれると、偲ぶものがなくなってしまって、寂しいですね。
−お二人の、演劇、あるいは平さんとの出会いは何がきっかけだったのですか。
福田:これ、昭和33年の文学座の『ワーニャ伯父さん』のパンフレットです。今はもうありませんが、渋谷の東横劇場で上演したのを観ました。下に電車が走っていますので、座席の下から電車が走る音が響いてくるような劇場でした。「良かったな」と記憶に残っているのがこの舞台で、もう60年も前のことになります。
私は函館生まれの函館育ちで、この当時は東京の大学で過ごしていたものですから、休みのたびに芝居を観ていました。『ワーニャ伯父さん』の最後の台詞が素晴らしくて。みんなが去った後、ワーニャ伯父さんとその娘が「毎日毎日暮れるともない夜をじっと生きて行きましょうね」というのが印象的でした。劇団民藝の『セールスマンの死』なんかも素晴らしかったですね。サラリーマンの方々が「身につまされるなぁ」って言いながら歩いているのを聞きました。
結婚して一年半で、長男を遺して夫が亡くなったもので、函館で社会の教師をして子育てをしました。でも、同じ母親として、平さんのお母様が平さんを愛おしんでおられた気持ちはとても良くわかります。
−いわゆる「新劇」の華やかなりし時代に芝居に出会われたんですね。
福田:えぇ。学生時代に観た芥川比呂志さんの『ハムレット』も、素敵でしたね。22歳まで東京でそういう時間を味わいました。
函館に帰ってからは、なかなか舞台を観ることはできなかったのですが、1986年の函館演劇鑑賞会例会「夢去りてオルフェ」で初めて平さんの舞台を観ました。テレビで観るのとは次元が違うのです。主人公の「桂木一機」を演じているのではなく、「桂木一機」その人になっているのです。劇場いっぱいに響き渡るセリフに酔いましたが、仕事や家事に追われ、平さんの舞台を観ることは出来ませんでした。少し時間のゆとりができ、上京して観たのが1998年の「王女メディア」で、「夢去りてオルフェ」から12年経っていました。
―土谷さんの場合はいかがですか。
土谷:私は、長門勇(1932〜2013)さんの晩年に近い頃、付き人を3年ほどしていて、それが本当の意味での、舞台と出会ったきっかけでしょうか。
−平さんの舞台の感想を伺って、「役者の思考・生理」をよくご存じだなぁと感じていました。そうした経験をお持ちだったんですね。
土谷:平さんが足を痛めても、観客には気付かれないように立つ場面などは、普通のお客さんは気付かないかもしれません。そういうところへ目が行くのは、同年代の長門さんの傍にいたことが影響しているのかもしれません。
−長門さんが亡くなった時の平さんのコメントの中の「『三匹の侍』は僕と長門さんが世の中に認知された作品だったので、とても思い出深い関係の方でした。ご冥福を祈ります。一緒に世の中に出た友として。」という言葉が凄く心に沁みた、と伺いました。
土谷:それが平さんファンになる一つのきっかけでもありました。長門さんが亡くなり、私にとって打ち込める存在が消えてしまいました。そんな、穴が空いたような気持ちの時に、折々に拝見していた平さんのテレビの『けものみち』と舞台の『リア王』に出会ったと感じ手紙を書いてしまったんです。
長門さんと同年齢でも、テレビや舞台でまだまだ主役を演じて、キラキラ輝いている平さんが、私が空虚な気持ちでいただけに、余計に眩しく見えたのだと思います。平さんは『三匹の侍』で長門さんと6年間スタジオで一緒でした。そんなご縁もありました。お二人とも、それで名前が売れて、長い年月、活躍されてきたのだなぁ、と感慨深いものを感じました。
―そういう時間を経て、平さんが土谷さんの前に「再登場」されたわけですが、決定的に惹かれた理由は何でしょう。
土谷:そこが一番不思議なのですが…。私の「瞼の父」が、割に背が高くてスッとした体型だったらしくて、その逆とも言える長門勇さんの役の温かさに父のぬくもりを感じてファンになったことから始まり、平さんに出会い、父親への複雑な想いに対して素直になれたことでしょうか。舞台の役者さんとファンの関係以外の物を私が感じてしまったんでしょうね。
−父への想い、ということですね。平さんは、土谷さんにとっては憧れの恋人でもあり、お父様のような尊敬や憧れの対象でもあり、ということでしょうか。
土谷:そうかもしれません。「戦争」を知っている世代で、自分の暮らしにはない時代や生活を通って来たお二人の中に、「夢の中の父」に似たものを見たのでしょう。同時に、『王女メディア』で目が合ったと勝手に自分で思った時、あのメディアの目に恋してしまったのかもしれません。
−ファンの方は、対象となる方にいろいろな想いを持ちますが、そういう点で、多くの条件を満たす存在が平さんだったのですね。
土谷:平さんが私にとっての「心の杭」になっていて、私が元気でいられるような気がします。同様に、長門さんも一本の「杭」として私を支えてくださって、それがあったからこそ、平さんのファンになる力を持てたのだなぁ、とも思います。
―では、次はお二人に、平さんの舞台の魅力を一言ではなく、たくさん語っていただきましょうか(笑)。
福田:前の蜷川さんが演出した『王女メディア』を観た時には、「凄いな」と思いました。それから、高橋惠子さんとおやりになった2001年の『近松心中物語』も素晴らしかったですね。高橋さんと二人で、目が合って、言葉もなくサッと動き出すところなんか、凄かったですね。観客をその気にさせてしまうんです。あの頃、もう60歳を過ぎておられたはずなのに、綺麗で色気があるんですよ。幕切れで雪がたくさん降りますでしょ。だから、帰りにバッグの中に紙の雪が入っていたこともありましたね。
土谷:私は、『王女メディア』が凄いと新聞で読んで、後から平さんのファンになってビデオで観て大ショックを受けました。2012年の時も『王女メディア』の記事を観て、DVDを買って。
その時も平さんにお手紙を書いて、家来たちから、メディア自身が計画した行為の凄惨な顛末を聞いている表情が素晴らしかった、と書いて、「もうやらないのは残念です」という熱烈な想いを書き綴ったのを憶えています。その時には、女性としての感覚を平さんに伝えて「こうしたら、もっと良くなるのではないですか」なんていうことまで書いてしまい、2015年に再演されるとわかった時は感動しました。
福田:今の時代は芝居もインスタントが多いですけれど、あれだけ芝居をキチンと創ってゆく役者さんも、もういらっしゃらないんじゃないでしょうか。
土谷:会ったこともないファンの長文の手紙を丁寧に読んでくださって。平さんからお返事をいただけるなんて夢にも思っていませんでしたので、びっくりもしましたし、何より嬉しかったです。長門さんにも長い手紙を書いたことがあったのですが、その時に『感動した、とか面白かったですのようなお手紙もありがたいけれど、場面や演技について感じたことを具体的に書いてくれて嬉しかった』と言われましたので、平さんも客席からの感想を待っているかもしれない、という気持ちはありました。思い込みかもしれませんけれど、演技の細かなところの感想に対する答えを、舞台で見せてくださっているのを観ると、平さんの舞台に少しは貢献できたのかなとも思います。
―そうしたことは実際にあると思いますよ。平さんが、キチンと自分の芝居を観てくださる方々の声や反応を、どれだけ真面目に受け止めていたか、ということではないでしょうか。
ファンの声は大きなもので、「こんなところまで観ていてくれたのか」という喜びは、役者でなければ分からないところでしょう。
土谷:手紙を通じて平さんと会話をしていたようで、嬉しかったです。ちゃんと応じてくださるから、私もまた長文の手紙を書いてしまうんですね。
福田:『王女メディア』は好きですね。最期の時も、「憎くて我が子を手に掛けるわけではない」という場面などは、舞台からグイグイ迫って来るような感じがしましたね。
−台詞まで覚えていらっしゃるんですね。
福田:一番前や二列目の席をくださることがあるので、本当に迫力がありますね。ただ、舞台は扮装していますでしょ。スーツ姿の「素」の平さんは、まぶしくて見られませんでした。
−それは、どこでご覧になったのですか?
福田:「平幹二朗友の会」のパーティの時です。ツーショットも撮っていただいて、これはもう、宝物です。
−「幹の会」は、平さん個人でもあり、「平幹二朗友の会」が名前を変えたものですね。2001年に第一回目のパーティが帝国ホテルで行われ、ファンの方々と交流されたと伺っています。その折に「僕は皆さんと運動会をしたりすることはできませんので」とおっしゃったそうですが、代わりに、舞台から芝居でお返しします、という意味だったのですね。
福田:その通りに、舞台からたくさんの物を我々に送ってくださいましたね。帝国ホテルのパーティでも、本当に素敵でジェントリーで、輝いているようなにこやかな笑顔は忘れられません。平さんとの写真はこれ一枚だけなのですが、だからこそ、余計に大事なんです。お願いすれば、お目にかかることができたのかもしれませんけれど、舞台で見せてくださるお芝居を味わうことで、すべて満たされてしまうような気持ちでした。本当に、「お芝居のために生きていらっしゃる」ことが分かるような舞台でした。
−まさに、パーティでのご挨拶を実践されていたわけですね。
土谷:お芝居のご案内やチケットも、いつも手書きの封筒で送ってくださって。筆まめでいらしたし、字も上手で、平さんからいただいたお返事は宝物です。私がチケット代を間違えてしまった時も、わざわざ現金書留で差額を送り返してくださったことがありました。そうしたら、福田さんが「あなた、金額間違えてよかったわね(笑)」って。
福田:そうよ。そのお返事も宝物よね(笑)。あれだけ立派な役者さんで、そういうことまでご自分でおやりになる方は、そんなにいらっしゃらないんじゃないでしょうか。
−そうですね。大体の場合は、事務所や、芝居の制作・広報担当などの仕事になります。今は、パソコンで住所シールが簡単に出せますから、手書きのご案内は貴重ですね。ご自分で席割をしながら、不公平にならないように、ファンの方々の顔を思い浮かべておられたのでしょうか。そうした作業も平さんには「楽しみ」だったのかもしれません。
−ところで、お二人はどういうきっかけでお友達になられたんですか?
福田:『黄昏のロマンス』の時に、土谷さんがお隣の席で、声を掛けてくださって、それから親しくお話するようになりました。
土谷:私は、その時は平さんの生の舞台を観始めて何度目か、という頃で、平さんに席を取っていただくようになったばかりだったんです。それで、「幹の会」に入りたかったのですが、福田さんに、その時は「幹の会」の活動はしていない、と教えていただいて。それから、福田さんが東京へお見えになる度にお目にかかっていろいろなお話をしています。
−福田さんは教職におられたということですが、考えようによっては述べ何千人という生徒は観客とも考えられますね。
福田:そうですね。誰でも、授業を真剣に聞いてくれている時は嬉しいですね。場合によっては、生徒の熱心さに自分が持っているものを引き出されることもありましたし。授業の場合は、一年間は相手は同じですけれど、芝居は毎日観客が違うというところでしょうか。
土谷:私は中学生の時に、先生にいろいろな質問をするので、「あの子は大丈夫かなぁ」って言われたぐらいで、平さんにも同じことをしていたんでしょうか(笑)。
福田:きっと、授業を真剣に聞く子だと思われていたのよ。
−お二人とも、平さんにとってよき観客であることはもちろん、時には何かの「ひらめき」をくれる存在だったのかもしれませんよ。
二人:(声を揃えて)そんな恐れ多いことはないでしょう。
−辛いお話になりますが、平さんの訃報を知られて、大きな衝撃を受けられたでしょうね。喪失感も相当なものだったでしょう。
福田:マンションの下へ新聞を取り行ったら、「北海道新聞」の一面の「今日の主なニュース」欄に「平さん」が出ていて、「あっ、平さんのニュースだ!」と思って急いで読んだら「えっ…」という感じでした。ニュースを知り、心配してくれた友達から電話がかかって来るんですが、一切出ませんでした。ああいう時には、言葉はいりませんね…。一人にしてほしかったです。
でも、「ここでグズグズ考えていても仕方がない。何もできないけれど、とにかく東京へ行こう!」と、飛行機に乗りました。それで東京へ着いて、土谷さんと連絡を取りました。
青山斎場の告別式には、入れないだろうから、外からでもお見送りを、と思っていたら、秋山さんのお計らいで中へ入れていただき、お別れをすることができました。それで、その時はようやく少し治まりましたね。
土谷:私が訃報を知ったのは、テレビや新聞ではなく、知り合いからのメールでした。「大丈夫?」というのが何本もあったので、嫌な予感がしてインターネットを見たら、そこに訃報が出ていて。その日、会社の朝礼で平さんの話が出て、ポタポタ涙を流してしまいました。何とか一日仕事をして、ようやく秋山さんにメールをして、斎場の中へ入れていただけるというので、お焼香もさせていただきました。そんな場面にも出させていただいて、「ありがとうございます」と満足できましたが、その後で大きな喪失感が来ましたね。
福田:お通夜の時は土谷さんともいろいろお話をして、お互いに気が紛れたんでしょうけれど、一人になるとね。
土谷:その頃、出そうとして下書きをしていたお手紙もあったんですが、それも全部破いて捨ててしまいました。「今まであんなにたくさん書いたのに、「これが平さんからのお返事なんですか」という想いでした。まだ観ようと思い、書きたいこともあったのに、突然に、というのは腹が立つような想いさえありましたね。やりきれなくて。
―大事な方を喪った時の喪失感は、だんだん大きくなる場合もあります。その中で想い出を話したり、想い出したりすることが「偲ぶ」ことでもあるのではないでしょうか。こうして皆さんに話していただくのもそうですし。
福田:改めて、平さんのお話をするとなると、凄く緊張しましたけれど、自分と平さんの歴史を振り返るきっかけにもなりました。
―多くの平さんの舞台をご覧になった中で、「三絶」はどれでしょうか。
福田:私は、『夢去りて、オルフェ』、『近松心中物語』、そして「幹の会」の『王女メディア』ですね。
土谷:私は生の舞台はあまり観ていないのですが、『王女メディア』、『唐版 滝の白糸』、ビデオですけれど『タンゴ、冬の終わりに』ですね。『クレシダ』は遺言のようになってしまったので、入れる気持ちにはなりません。
福田:『クレシダ』は「白鳥の歌」のように感じました。いつもは二回観るんですが、これだけは土谷さんとなぜか三回観ました。
土谷:平さんは、『クレシダ』の時に、稽古の段階から役をどう作るか悩みとやりがいを新聞のインタビューに語っていらっしゃいました。公演では喉を傷めていらっしゃるのも感じ、「励まさなくちゃ!」と思って、やはり生の意見も必要なんだと思って、立派なプロの方のような原稿は書けませんけれど、平さんの何かにお役に立てれば、と思って書いたんです。そうしたら「嬉しく読みました」っていう言葉を書いてくださって。
−汲めども尽きぬ平さんへの想いを、長時間にわたりありがとうございました。今日はお二人からお話を伺いましたが、同じようなお気持ちの方も大勢おられるでしょう。泉下の平さんにとっては役者冥利ですね。
またいつか、想い出をお聞かせください。