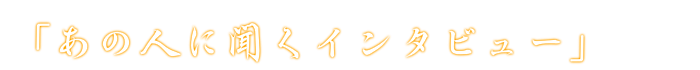
聞き手:中村 義裕(演劇評論家)
第六回「熱き心に宿る平さんの魂」
三浦 浩一さん(俳優)
このコーナーは、平さんとゆかりの深かった方々に、さまざまな想い出をお話いただくコーナーです。

今回は「三浦浩一さん」。いつも変わらぬ爽やかさで幅広い役柄を演じている三浦さんは、今年でデビュー40年を迎えた。一世を風靡した劇団「東京キッドブラザース」時代から、さまざまな役柄や経験を経ているベテランに平さんへの想いを聴いた。場所は前回と同じ平さんが愛したお店で、店主の心づくしの平さんが愛したメニュー、「平さんコース」に舌鼓を打ちながら、想い出を語っていただいた。
−平さんとの共演は、2010年の『冬のライオン』が初めてですか?
三浦:平さんと同じ舞台に立ったのは、2006年の明治座での『剣客商売』が最初ですね。あの時は、出演予定だった藤田まことさんが病気で降板されて、平さんは代役での主演でした。その時に、「時代劇でのこういう役柄は初めてなんだよ」とおっしゃって、いろいろな工夫をされながら役作りをされていたのを覚えています。稽古でも、やる度にドーランの色が違うんですよ。そんな役者に初めて会いました。どうやったら、自分が少しでもその役らしく見えるか、というこだわりが半端ではないんですね。僕も役柄によって考えることはありますけれど、こだわり方が全然違いますね。
映像では、それよりも前にご一緒させていただいています。NHKのお正月時代劇で、それが最初にご一緒した作品になります。1980年に僕がNHKドラマ『風神の門』の主役をやらせていただいて、その後のお正月の特別番組でした。その時、初めて平さんと面と向かったんですが、平さんの台詞がものすごい量の説明台詞だったんです。役者にとっては、状況を説明するだけの台詞は、あまり心地よいものではないんですよ。それが、リハーサルの時にはほとんど頭に入っていて、必死に想い出しながら台詞として言葉にするのを見て、「わっ、本物の役者だ!」と思いました。それほどに衝撃的な出会いでしたね。
−「幹の会」では2010年の『冬のライオン』での共演となりますが、この時はいかがでしたか?
三浦:あの作品は苦労した舞台ですね。演出家の髙瀬久男(1957〜2015)さんのダメ出しはすべて僕、のような感じで、稽古場に出かけるのが嫌になって、かみさんに「もうダメだから、降りようかと思う」ってこぼしたこともあります。そうしたら、かみさんが「何を言ってるの、ありがたいと思いなさいよ。今、そんなことを言ってくれる演出家なんていないんだから」と、背中を押してくれて何とか乗り越えましたね。
芝居の世界に入って、「東京キッドブラザース」という劇団で、勢いと情熱だけで突っ走る、みたいな芝居が染み付いていたのを、髙瀬さんが根気よく剥ぎ落としてくれたことは本当にありがたかったです。加えて、平さんの強烈な役者ぶりを毎日眼にすることもできて、本当に忘れ難い舞台になりました。あのツアーのメンバーはお酒が好きな方が多くて、本当に良く飲んで、楽しいツアーでしたね。
−三浦さんは、映像は言うに及ばず、舞台でも相当に小劇場から大劇場まで、幅の広い役柄を演じておられますね。その中で、髙瀬さんのようなタイプの演出家は初めてだったのではないですか。
三浦:手の上げ下げから身体の向き、台詞の音程や間、とにかくありとあらゆることを直されました。毎日恐ろしいほどの量のダメ出しが来て、台本は書き込みだらけでしたね。台詞よりも書き込みの量が多いんじゃないか、っていうぐらいに(笑)。ただ、そういう鍛え方をしていただいたのは初めてで、本当に勉強になりました。東京キッドの頃は、主宰者の東由多加(ひがし・ゆたか:1945〜2000)は何も言いませんでしたし、仲間と演技論を闘わせたこともありませんでした。『冬のライオン』で髙瀬さん、平さんに出会ったことで、役者としての考え方も変りました。そういう意味でも、僕の役者人生の中では大きな作品です。
−今、お話に出た「東京キッドブラザース」、懐かしいですね。1968年に結成されて、三浦さんが入られた頃は、柴田恭兵さん、奥様の純アリスさんなどが凄い人気でした。のちに三浦さんとの三枚看板で、若者の絶大な人気を得た劇団で、私も拝見していますが、勢いのある「熱い」舞台が、多くの若者の人気を集めましたね。三浦さんは、なぜ「東京キッド」へ入られたのですか?
三浦:子供の頃は、マンガ家やボクサー、レーシング・ドライバーなどに憧れていました。父は決まった時間に出て決まった時間に帰って来る、昔の典型的なサラリーマンだったのですが、子供ながらに「僕にはこういう仕事はできない」と。自分の身体一つを元手に勝負する世界に憧れていたんでしょうね。
中学二年生の時に、父の仕事の関係で岐阜へ転校して、そこで映画館へ通うようになりました。ジェームス・ディーンの映画や『ウエストサイド・ストーリー』、『風と共に去りぬ』のように、いまだに語り継がれている名作の数々に出会って、スクリーンに憧れたんですよ。それで、「俳優っていう仕事があるんだ」と。役者になれば、どんな職業に扮することもできて、すべての憧れを満たせますからね。
高校へ行く気もなくて、岐阜から東京へ出て、文学座や俳優座などの養成所を受ける気でいました。ただ、父が「高校ぐらいは行け」と言うので、高校へ行ったら剣道部の顧問の先生が全日本で二位になった人だったんですよ。たまたまその試合をテレビで観たことがあって、その時は知らなかったのですが岐阜の小さな高校の剣道部の顧問が、その先生だったんです。本当は演劇部に入ろうと思っていたんですが、こんなに凄い先生がいるのなら、と剣道部に入りました。そこで心と身体を鍛えてもらったおかげで、挫けることなく、何が何でも俳優になろうという想いを貫けました。今考えると、平さん、髙瀬さん、東由多加、剣道部の村瀬先生、その時その時に素晴らしい人々に出会えたことが僕にとっての宝物ですね。
―俳優を目指したことへの反対はありませんでしたか?
三浦:特に反対はされませんでした。きっと、なれるとは思っていなかったんでしょう。高校へ行ったら「じゃあ大学へも」と言われて。でも、そんな気はないし、勉強もしていないから無理なわけです。ただ、行くなら「日大芸術学部映画学科」が目標ですが、行けるわけはないですよね。それが、奇跡のように入れてしまって。父にしてみれば、子供の幸福を考えて、「せめて学校だけは」という想いがあったんでしょうね。大学二年の時に母が亡くなり、死の間際にベッドで母の手を握って「オレ、絶対に俳優になるから」って言って。それで大学を中退して、アルバイトをしながらあちこちの養成所を受けたり、テレビ局の小道具係をやったりしました。
一年ほどそんな生活をしていて、新宿西口の「三銃士」っていうバーボンハウスで、時給360円でバーテンのアルバイトをしていました。ある日の夕方、開店の準備を終えて、店にあった新聞を何気なく見ていたら、「東京キッドブラザース オーディション」っていう記事があったんです。まだ、その頃、「東京キッド」の舞台は観たことがなかったんですが、ニューヨークへ行って『黄金バット』が大ヒットしたなどのニュースは知っていました。その頃は映画に憧れていて、板の上で芝居をするとも思っていなかったので、あの「東京キッド」か、と思って、オーディションだけでも受けてみようかというのが役者へのスタートです。あの時、新聞記事を見ていなければ、僕はオーディションも受けていなかったでしょう。節目のことを考えると、いつもスレスレのところで来ているような気がしますね(笑)。
僕が入った頃は、一時の爆発的な勢いが少し失われかかっていた時期でした。でも、柴田恭兵さんや純アリスがいて、そのうちに僕も何とかやれるようになって、また盛り返したんです。僕は、まだぺーぺーでしたが、柴田さんとダブル・キャストで役をやれるようになり、いろいろな方々が観に来てくださいました。それが1980年のNHKの『風神の門』の主役の抜擢に結び付いたんです。これはもう「奇跡」ですよ。
「東京キッド」ではアルバイト禁止で、親の脛をかじるぐらいしか方法がないんです。ろくに食べられないから、メインの役者や制作に付いて歩いていると、呑めて食べられたんですよ。最低限の生活で精一杯だから、呑みに行く余裕なんかなくて、それが嬉しかったですし、楽しい時代でした。
今の考え方で行けば「そこまでしなくても…」ってなるんでしょうが、主宰の東の「この世界で生きて行こうと思うのなら、アルバイトなんかするな」という、僕たちに対する愛情だったんでしょうね。「芝居一本で食えるようになれ。演じることで金を稼げ」と叩き込まれました。それは感謝でしたね。
初めてもらった給料が40,000円でした。新大久保の居酒屋だったところの内装を役者皆でぶっ壊して、365日芝居を打っている「シアター365」という小さな劇場を造って、毎日芝居をやっていたんですよ。だから、何とか食べて行けるだけの給料がもらえて。これは、劇団四季よりも先だったんじゃないですか。その頃の40,000円は一ヵ月暮らすのがギリギリの金額でしたね。かろうじて生活しながら芝居をやれるという体験があったから、「武道館公演」なんていう凄いことができたんでしょうね。
−改めて伺うと、平さんと三浦さんは全く線がクロスしないほどに年代も役者としての歩みも全く違いますね。役へのアプローチも違うとは思いますが、そんな二人の出会い、も面白いですね。
三浦:だからこそ、僕にとっては強烈な出会いでしたね。テレビの収録で、自分の中で、どこかに「まだリハーサルだし、本番で勝負すればいいか」みたいなところがあって。カッコよく言えば、段階が進むごとに創り上げて行こうという想いがあったんでしょうが、平さんはいきなり100%でぶつかって来られたような印象でしたね。
いろいろなタイプの俳優さんがいて、良い悪いではなく、一度芝居を決めてしまったら変えない方もいらっしゃいますよね。平さんはそういうタイプではなく、その場の空気や僕たちとの呼吸や間合いを考えて、芝居をしていました。僕もそれを目指して、舞台の上でその瞬間を生きている人物の表現、にはこだわりますね。それは、『冬のライオン』も『王女メディア』も同じでした。
−私もいろいろなジャンルでの三浦さんの舞台を拝見していますが、芝居に嫌みがないのが大きな魅力だと思うんです。例えば、演出家によって、「この舞台は紫色」「これは緑色」という構想があると思いますが、どこかに絶対に染まらない「白」の部分があって、そこが三浦さんの核になっている部分なのではないか、と。その色は、他の色ではなく「白」だからこそ、何をやっても爽やかな風が吹くように感じるのではないか、と思うんです。
三浦:テレビでも映画でもさんざん犯人などの「悪」をやりましたけれど、完全な悪にはなり切れないんです。役者としてはいけないのかもしれないけれど、そこまで行くと、「嫌な人」になってしまう。自分なりに役を考えて現場へ行きますが、僕の白い部分をどういう色にでも染めてくれるのが監督であり、演出家という存在。そういう点で、今までの僕と違う部分を引き出してくれたのは高瀬さんで、恩人ですね。それがあったから、平さんや麻実れいさんと同じ舞台に立つことができたわけですから。その結果、今までの芝居にはなかった新しい抽斗を創ってくれた、とも思います。
−平さんは、そういう場面を観ていて、いろいろ感じられたのだと思います。これは想像ですが、稽古場でメタメタになっても、宿題を片付けてまた次に挑む姿勢を、好ましくご覧になっていたのではないでしょうか。平さんは、稽古場で「苦しめる」人や「自分と闘える」人が好きだったんじゃないでしょうか。自分で限界を決めたり、投げ出してしまわないような。
三浦:諦めなくて本当に良かったと思います。髙瀬さんにダメを出されたところを自分なりに消化して、答えがOKではないのかもしれないけれど、何とか喰らいつくのを観ていてくださったんでしょうね。共演の若い役者さんたちが、集中攻撃を喰らっている僕を心配してくれて、稽古の後で呑みに誘ってくれ、そこでガス抜きができて救われたこともありました。
その後、本番の幕が開いて、僕がやっていた長男の役をお客様が誉めてくださると、「あの稽古をくぐって、耐えた甲斐があったなぁ」と思いましたし、改めて髙瀬さんの恩を感じましたね。演出家は、少しでも作品の出来を良くするための仕事として、僕を徹底的にしごいてくれたんだと思います。
−そうした経験を経て、2016年の『王女メディア』になるわけですね。
三浦:『王女メディア』では、舞台に立っている平さんの姿を残して置こうと、心の中で何百回もシャッターを切りました。それは財産だし、「やろうと思えばここまでできるんだ」というお手本ですから。人間なんて怠けようと思えばいくらでも怠けたくなるものじゃないですか。でも、82歳であそこまでやれる人がいると、63歳の僕も「よしっ! まだまだ頑張るぞ」と思えるんですよ。その日、その時、その瞬間の真剣勝負を重ねて行かないと、と改めて思います。どんな仕事でもそうでしょうけれど、「これでいい」と思った瞬間にストップですよ。平さんも千田是也さん、浅利慶太さん、蜷川幸雄さんという素晴らしい演出家たちに出会って、そこで吸収したから、あんなに凄い役者になれたんだと思います。
水戸の千秋楽で、「今回もお世話になりました」って挨拶に行った時に、最高の笑顔で握手をしてくれたことを、今でも忘れられないんですよね。平さんが、今までずっとやって来た中で、満足のいく舞台ができた喜び、あの笑顔と温かい手の感触は僕の宝物ですね。
舞台は生ですから、その一回で全力を出し切らないと。全身をさらして演じているんだから、どこを切り取って観られてもOK、っていう状態でいないとダメなんじゃないですかね。でも、「生」でやり直しのきかない怖さがありますから、それに耐えられないとチャレンジはできないですよ。その分、恥もかくし、悔しい想いもするけど、役者としてはまず「舞台」がありき、だと思いますね。
−2016年、96ステージに及ぶメディアの旅、役者として、あるいは個人としてどうお感じでしたか。
三浦:やはり「メディア」として観ていましたね。平幹二朗なんだけれど、メディアの存在の方が大きかったように思います。幕切れに夫とやり合うところでは、僕は村の女の一人として、臥せったままで二人のやり取りを聴いているんですけれど、二人の間でスパークするような感情を、平幹二朗と山口馬木也ではなく、メディアと夫とのやり取りとして聴いていましたね。だからこそ、自分の中で何回もシャッターを押すという感覚になったんでしょうね。本来、それは「役者」としてはよくないことで、一瞬、三浦浩一に戻ってしまうわけです。ですが、それでもそう考えてしまうほど、迫力にも満ちていたし。今にして思えば、長い旅だったけれど、残りが少なくなって来るにしたがって、一回一回が愛おしくなったんでしょうね。
もっといろいろな事を質問していれば、平さんは間違いなく的確な答えを返してくれたでしょう。でも、あえて聞かずに、稽古場で見たものを吸収しようとしました。僕は「演劇論」みたいなものが苦手で、現場で役者が動いたり苦しんだりしている中で「何か」を吸収する方が性に合っているんです。議論を闘わせることを否定はしないし、そういう場面もあるべきなんでしょうけれど、僕は身体と頭でどこまでやれるか、っていうタイプなんでしょうね。
−三浦さんは感覚が若くて、熱いですね。鹿児島県出身だからか、桜島火山のような熱さ、を感じます(笑)。「燃える60代、三浦浩一」
という感じですね。
三浦:それは、平さんのように、いくつになっても輝いていたい、っていうことなのかなぁ。今からでも、吸収できるものは何でも吸収して、自分を常に変えて行かないと、ダメなような気がして。惰性で生きないで、いい物にいっぱい刺激を受けて、もっと魅力のある役者になりたいと思うんですよ。スポーツもやりたいし、いい音楽や絵にも触れたい。子供の頃は漫画家になろうかと思ったぐらいだから、美術展や写真展に出かけるのは、刺激を受けたいんですね。後悔する人生を送りたくないので、常に未来を考えながら、というところはありますね。
−そういう方だからこそ、平さんが必要とされたんでしょうね。
三浦:もう一度、芝居がやれたらよかったなぁ…。
−平さんはやりたかったのではないでしょうか。「『王女メディア』、みたび」を。そんな気がしてなりません。
三浦:ええっ!…そうかもしれませんね。でも、やっている最中は「最後のメディア」だと思ってやっていました。もし、まだ次があるな、という気分があったら、良い舞台にはならなかったとも思うんですよ。
−ところで、三浦さんは、どうしてそんなに若々しくいられるんですか。
三浦:「ここで終わってたまるか」っていう気持ちですね。いい年なんだから、大人の男として振る舞いたいけれど、精神年齢は28歳ぐらいで止まっちゃっているんじゃないかと(笑)。それと、変な意味ではなくて、何かに「ときめく」ことかもしれませんね。
もう一つは、年を重ねても、変に固まってしまいたくないんですよ。これからの芝居は、若い人が観たいもの、感動するものをどうやって造るか、だと思うんです。10月に、渋谷で39年ぶりで、東京キッドの『失なわれた藍の色』という作品を、次男の孝太、三男の涼介と一緒にやるんですよ。僕がやった役を孝太が、柴田恭兵さんがやった役を涼介がやって、僕は劇団のベテランがやっていた呑み屋のマスターの役をやるんですが、どうなるのかなぁ。今の若い人たちにああいう芝居が受け入れられるのかどうか、心配でもあるし、「よしっ!」っていう気持ちにもなりますね。
−三浦さんの原動力を垣間見たような気がしました。カウンターのいつもの席で、平さんも微笑みながら聴いておられるようでしたね。長い時間、ありがとうございました。
「対談」の場合、話を聴く側を「インタビュアー」、話す側を「インタビューイ」と呼ぶ。三浦さんは、インタビューイとしての人間的魅力に溢れていた。硬軟取り混ぜた楽しい話が終わり、平さんが愛した美酒・美食にみんながいい気持ちに酔った。かなり遅い時間に店を出た時に、一陣の風が吹き抜けて行った。あの風は平さんだったのだろうか…。

「芝居の話になると、活火山からマグマが噴き出すような勢い。平さんとの舞台での真剣勝負の源泉がここにある」

「感じよく肩の力が抜けている「微醺」の三浦さん」

「真面目な話題のはずだが…。三浦さんの人柄だろうか」

「平さんがいつもいた場所で、平さんの好きなワイングラスに語りかけている三浦さん。この後、三浦さんは『いただきます!』とグラスを干した」
三浦 浩一(みうら・こういち)
1953年鹿児島県生まれ。1977年、「東京キッドブラザース」にて俳優デビュー。80年、NHK『風神の門』にて主演デビュー。以後、活躍の場をテレビ・映画・舞台へと広げ、84年『スクール☆ウォーズ』、93年『高校教師』、93年『炎立つ』(ほむらたつ)などのドラマで人気を博す。
舞台では名古屋・御園座、東京・明治座の『剣客商売』、「幹の会」での『冬のライオン』、『王女メディア』、全国ツアーの『4フィール』など、多彩な作品に出演し、その爽やかさと存在感が安心した芝居を見せている。
2017年10月14日(土)〜22日(日)、渋谷・シブゲキ!!にて、「東京キッド」で1978年に上演され、大きな話題を呼んだ『失なわれた藍の色』を次男の三浦孝太、三男の三浦涼介と共に親子共演の幕が開く。
三浦浩一★今後の予定
Sweat&Tears東京キッドブラザース44th 『失なわれた藍の色』
『失なわれた藍の色』
SBGKシブゲキ‼


 音楽劇「赤毛のアン」
音楽劇「赤毛のアン」
11月17日~19日 5公演
東京国際フォーラム ホールC




