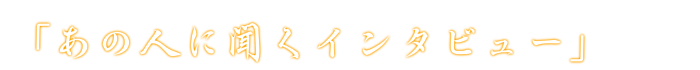
聞き手:中村 義裕(演劇評論家)
第五回「私が見た平さん」
廣田 高志さん(俳優)
このコーナーは、平さんとゆかりの深かった方々に、さまざまな想い出をお話いただくコーナーです。

都内某所のお蕎麦が美味しい和食店。美食家でもあった平さんが、時によっては「週に五日」のペースで足を運び、美味しい料理とお酒を静かに味わい、楽しんでいたお店が今回のインタビュー会場だ。亡くなる二日前にも訪れ、その頃、廣田さんが川崎で出演していたシェイクスピアの『真夏の夜の夢』の舞台を、「ちゃんとできてるのかなぁ、あいつ」と気にかけていた、と店主さんから伺った。
カウンターの奥の、平さんがいつも座っていた席には、平さんが愛した白ワインがグラスに満たされ、もう二度と訪れることのない主を待っている。「平さんが聴いているかもしれませんね」と言いながら、平さんの想い出話に時を忘れた。
−廣田さんは、「幹の会」のプロデュース作品には、一人芝居の『親鸞 大いなるみ手に抱かれて』以外は全作出演されていますね。いろいろな平さんの姿をご覧になったでしょう。一言では難しいでしょうが、「平 幹二朗」という方は、どんな印象ですか?
廣田:初対面の時は、とにかく怖くて、眼も合わせられませんでした。「おはようございます」「お疲れ様でした」「ありがとうございました」の三言がやっと、のような。特に、その頃の平さんは「シェイクスピアと言えば平幹二朗」という評価が世間にもありましたし、自信に満ち溢れていたように感じました。
稽古場に入った時から、すでに他の役者とは意気込みが違っていて、僕らのようにジャージなどではなく、キチンと役の衣裳を工夫して見えていました。「稽古場は、役者としてのプレゼンテーションの場なんだ。自分なりのプランを演出家に見せる場所でもある」と教えていただきました。
どの舞台でもそうでしたが、「この一回」に命を賭けておられましたから、舞台でトラブルがあると「今日のお客さんが観られるのはこれ一回なんだよ!」と怒られましたね。とにかく、すべて芝居のために生きているような方で、稽古場まで身体を鍛えるために歩いて来ること、食べること、呼吸までもが芝居のためじゃないか、というぐらいでした。
−それが最初の印象ですね。廣田さんは、劇団「文学座」所属の俳優さんですが、平さんとの共演のきっかけは何だったのでしょうか?
廣田:1992年に、京橋にあった銀座セゾン劇場(その後、「ル・テアトル銀座」と改称、2013年に閉館)で平さんと夏木マリさんで上演された『タイタス・アンドロニカス』に出演させてもらったのが最初です。今から25年前、まだ「幹の会」の活動が始まる前のことです。
この舞台に出ることになったのは、実は偶然で、最初は他の役者の予定でした。マネージャーが文学座のアトリエへ探しに来た時に彼がいなかったので、背の高さを買われて、出演が決まったような形でした。平さんは体格が立派ですから、周囲に立つ兵士なども、それなりの身長がないと舞台面のバランスが崩れてしまうんですね。
−ラッキーな偶然でしたね。
廣田:はい。ここでの平さんとの出会いがなければ、それ以降全くなかったか、あったとしても相当に遅れていたでしょうね。
−ところで、廣田さんはなぜ俳優に?
廣田:僕は愛知県で生まれ、父の仕事の関係で中学三年まで北海道の苫小牧と江別で過ごしました。父が東京の本社へ帰ることが内定し、高校は川崎の叔父の家に下宿をして通いました。クラスメイトの中に、当時の人気番組『金八先生』の生徒役の子がいて、その子に触発されたんです。
浪人して、日大の芸術学部の映画学科、演劇コースへ入りました。二年生の時に、教授から「力試しにどこかを受けてみては…文学座がいいのでは」と言われて。その頃は何も知らず、力試しと思って行ったら受かったんです。上智大学で筆記試験の後、二次試験が文学座のアトリエで「身体表現」でしたが、アトリエで受験生の案内をしていたのが渡辺徹さんでした。
一年間休学をして、「研修科」に上がれなかったら大学に戻るという約束で親の脛をかじり、研修科に上がれたので、大学を辞めました。あの時の教授の一言がなければ、サラリーマンになっていたかもしれませんね。
初舞台は1988年に江守徹さんが南座で上演した『マクベス』でした。いきなり南座の大きな舞台で、もちろん台詞はなく、兵士や貴族といくつもの役をやりました。
初舞台は両親が観に来ましたが、文学座を受ける時には反対されました。和室で正座をさせられて、父に「河原乞食になるのか!」と言われて。何分間かの無言の「間」の後、「俺は、お前がやろうとしている世界のことはわからん。だから、何の手助けもできない。ただ、「自殺」の一歩手前まで行ったら、俺のところに来い」って。その時は泣きましたね。
−カッコいいお父様ですね。その後、役者として多くの舞台を経験されていますが、平さんとの共演が一番多いことになりますね。
廣田:僕が役者になって、今までに87本の舞台に出ていますが、そのうち平さんとの舞台が、「幹の会」以前の物を含めて33本あります。「幹の会」の舞台で、三田和代さんや剣幸さんなど、一流の女優さんを相手役に平さんが鎬を削る姿を舞台の上で勉強できたのは、役者として幸せだと思います。
今のような話でその想い出をたどると、平さんなくして、僕の芝居人生はなかったのだ、と改めて感じます。
稽古場でも楽屋でも、ずいぶん叱られましたが、芝居のクオリティを上げるために命を賭けている平さんの姿勢を感じた瞬間でもありました。
−具体的にはどんなことで叱られたのでしょうか?
廣田:2000年の『シラノ・ド・ベルジュラック』の時、稽古中の夜に電話があって「できないんなら、辞めてもらっていいよ」と言われたことがあります。僕のやり方に、ぬるい部分があったんでしょうね。どんな細かいところもキチンと観ていましたからね。
何かの時に言っておられましたが、台詞の言葉が、役の言葉で、「役の人間」として血肉の中から出てくる言葉になっていなかった、ということです。
この時は酔っ払いの役で、見た目のイメージや印象だけで演じてしまって、なぜそういう状況になっていたのか、という役のバックボーンを掘り下げていなかったことがいけなかったのだと思います。
−演出家によっては、よく「役の履歴書を考えろ」と言いますが、同様の感覚ですね。
廣田:そうですね。2001年の『冬物語』の時は、平さんが初めて演出家としての役割も担っていました。その時から、平さんは「フレージング」という演出法の一つを使われました。
−演出家としての平さんはどんな感じだったのでしょうか。また、「フレージング」とは、どういう稽古法なんでしょう。
廣田:「フレージング」は、息継ぎのところで台詞を切って、そこで変わる感情の動きを書き出し、その気持ちで台詞を言う稽古法です。「フレージング」をすることで、本読みの時に一つ一つの役の性格やそれまでの人生を掘り下げて、役が人間として生きることを感じ、ものすごく勉強になりました。
こうして、自分の身に付く勉強をさせていただいたことは大きいですね。ただ、感覚が鋭いので、こちらの気が緩んでいる瞬間、100%でやっていない時がすぐにわかってしまうんです。ご自分は常に「100%」を求め、目指している方ですから。どんな気持ちや肉体条件で稽古をするのか、ということを自分自身に問う経験にもなりました。
単独で演出をされる時の平さんは、役者・平幹二朗と演出家・平幹二朗との二つのアンテナが、時にクロスしながらカメレオンのように動いているのがよくわかるんです。アンダー(代役)として僕に芝居をさせながら、そこで「自分はどうするべきか」を考えている平さんもいました。頭の中のキャンバスに、動きなどの絵を描いているような感覚で、すぐにでも演出家の席から立って来そうな感じでしたね。扮装をして演出家の席に座っているわけですから。あの大きな眼は迫力がありましたね。
最期になった2016年の『王女メディア』のツアーでも、数えきれないほどのダメ出しで、ストレスで胃の具合がおかしくなるほどでした。旅も後半になって、會津若松の公演の時に、舞台が終わって「おい、飯食いに行こう」って声をかけてくださって。二人で雪の上を歩きながら、「おい、楽になったろう」と言われた時には、涙が流れました。結局、僕がいろいろな試行錯誤で苦しんでいる姿も何もかも、全部お見通しだったんですね。
−「會津」という事は、半年以上に及ぶ旅公演の後半戦も終わりに近い頃ですよね。それまで、毎日のようにそうした状態が続いたんですか?
廣田:忘れた頃に言われる、という感じでしたね。何かの用事のついでに「今日の芝居じゃだめだ。やりたいことはわかるようになって来たけれど、あれじゃ伝わらないね」とか。幕切れに、剣を置いてひざまずく場面があるんですが、思い切って、そこで立ち上がって芝居をしてみたんです。何もおっしゃいませんでしたが、そういうチャレンジを、もっと若い頃にぶつけられていればよかったんでしょうね。
−廣田さんの役者としての「ありよう」や「心構え」について、ですね。
廣田:自分ではいろいろなことをやって見せたくても「失敗した時に何か言われたくない」と、僕自身がシャッターを降ろしていたんでしょうね。芝居のプランを変えて、今度は右、左とウインカーを出すわけでもなく、ただ、まっすぐな道路を安全運転で走っていた、ということだと思います。
−ところで、平さんのツアーは半年以上をかけて細かくいろいろな土地を回りますね。私も、2010年の『冬のライオン』は福島県のいわき市で観ました。地方公演は「団体行動」ですから、そこでの想い出もあるのでは?
廣田:『冬のライオン』は、平さんもツアーを楽しまれていたようでした。出演者も7人しかいない舞台でまとまりが良くて。作品自体が夫婦や親子、家族の確執がテーマだったのも大きかったのでしょう、途中からは本当に家族のような感覚になって。移動が終わると食事会をして、みんなでよく呑み、よく食べました。
そういう時はお茶目な部分も見せて、楽しい旅でした。ある時、若手でボウリング大会を企画したんです。まさか平さんが来るとは思わなかったのですが、結局は全員参加になりました。でも、平さんは1,2フレームしか投げなくて(笑)。
−そうした「遊び」も、平さんには芝居漬けの日常をリフレッシュする一つの方法だったのでしょうか。あるいは、遊びに興じる後輩たちを見ながら、自分の「芝居の抽斗」の中に何かを仕舞っていたのかもしれませんね。
ところで、全作品の中で一番印象に残っているのは?
廣田:やはり『王女メディア』ですね。平さんは「初演の時は『復讐』に重きを置き過ぎた」とおっしゃっていて、再演の時は、演出家も替わりましたので、初演の演出を踏襲しながら、その中で何ができるか、を考えておられましたね。「復讐は結果論で、そうせざるを得なかった女性の苦悩を突き詰めたい」ともおっしゃっていました。
−2016年版では、「赦し」も大きなテーマになっていましたね。
廣田:そうですね。平さんの感情がさらに深まっていたように思います。例えば、復讐が成就した時の「ほっ」というため息に込められた感情、苦悩の深さが、再演では全然違っていました。
神や夫、周囲の人々、そして自分への「赦し」が幕切れの瞬間に感じられるからこそ、感情の激しさがより増幅されて見えるような芝居だったと思います。初演の時は、極端な言い方をすれば多くの感情やそれに伴う行動が「メディア」から発信されていたように感じたところも、再演では舞台全部から感じられるような感覚がありました。舞台全体の濃度がさらに高まった、ということだと思います。
−初演はメディアの意志で芝居を運んでゆく、再演の時は、周りの意志も見えない力で働き、やむなくそちらへ進んでしまった、というようなことでしょうか。
廣田:そうですね。幕切れへたどり着くまでの感情の紆余曲折が、初演よりも相当に多かったのではないかと思います。「赦し」にたどり着くまでの内面の葛藤が凄ければ凄いほど、「赦し」の意味も大きなものになりますよね。初演の時は、「憎しみ」の感情がストレートにぶつかるような勢いがありましたけれど、再演では、身体の中から滲み出るような印象でした。
−水戸の帰りに東京までご一緒したのですが、その時に、「やっと今日、初日が出たような気がする」との言葉が印象的でした。
廣田:僕も、水戸の公演が終わった後「やっとメディアができたかなぁ」と聞いたことがあります。
今想えば、ですが、広島での移動日に安芸の宮島へ出かけた時に、厳島神社の中を歩きながら回廊の外にある古びた能楽堂を長い間眺めていたことがありました。劇場だけではなく、地方のいろいろな場所で「メディア」をやりたい、と思っていたんでしょうね。どこの劇場でも、「次に『王女メディア』をやる時にはどうかな」と考えていたような気がします。特に、幕切れで本当に天空へ飛び立つかのように釣り上げることができるかどうかを考えていましたね。
−常に「進化する」ことしか考えておられなかったんでしょうね。
廣田:何かのビデオを観ていても、「おい、廣田、あれ使えないかな?」としょっちゅうおっしゃっていました。何をしていても、何を観ていても、自分がやる芝居のことしか考えていなかったのだと思います。多方面にわたって造詣が深く、若い頃は、ダメ出しをされても、その例えがわからないことがありました。「芝居だけやってればいい、ってものじゃないんだよ」とよく叱られました。
その影響でしょうか、美術館へ出かけるようになりましたね。作品を観て、これは何を表現しようとしているのだろうか、この時の作者の心象はどうだったのだろうか、など。一枚の絵からどれだけの「感覚」を自分が感じ取れるか、を勉強しています。
平さんは、常に前だけを向いていたように思います。もちろん、過去を振り向くこともありましたけれど、済んだことはもう終わり。「これから何ができるか」「どうするか」という情報の収集にも貪欲で「便利だ」と納得すれば、80歳に近くなってからやスマートフォンの使い方を勉強したりと何事にも意欲的でした。
最近は「一生懸命努力する」という言葉に、何かを感じていたようで、耳にする機会も多かったです。ある時期から、「下手でもいいから一生懸命努力する奴と芝居をしたい」とおっしゃるようになりましたが、若い役者が下手でも懸命に取り組む姿勢を観たかったのではないでしょうか。
−舞台だけではなく、平さんのリラックスした姿も、一人の役者を知る上では貴重なお話ですね。「役者・平幹二朗」と「人間・平幹二朗」を知ることができたのは、幸せでしたね。
廣田:お客さんが知ることのできない姿を見て来てはいますね。平さんは、好奇心が旺盛で、「貪欲」とも言える部分を持っていましたね。若い人の持っているアクセサリーやファッションにもとても興味を持っていて、例えば「ミサンガ」なども、「それは何?」「何に使うの?」「どこで売っているの?」とか。「今」という時代がどう動いているのかを、様々な角度から知ろうとして、すべてを「芝居」に活かしたかったんでしょうね。
旅公演でも、最初の頃はベテランの方々との会食が多かったのですが、だんだん若い役者を連れて行く機会も増えました。「今、何が流行っているの?」「若い人のファッションは?」など、「今」を知りたがりましたね。「好きな芝居は?」と聞かれても、「今やっている芝居です」とお答えになっていましたから、平さんは、「今」を生きることに一生懸命だったのではないでしょうか。
−それほど芝居に熱情を注いでおられた平さんの人生の幕切れは、今考えても信じがたいような気がします。
廣田:いまだに亡くなったことが腑に落ちないんです。また携帯が鳴って、「明日からよろしくね」と言われそうな気がして。旅公演で、モーニング・コールが遅れて叱られる夢もよく見ます。
平さんとは25年、女房とよりも長いお付き合いでした。ただ、それ程長いお付き合いをさせていただいたのに、最期があまりにも唐突すぎて…。それは、多くの方が感じていらっしゃることなのでしょうが、僕自身もまだ本当にお別れができていない、という気持ちで、整理が付かないんです。お通夜は晴天で、それが翌日の告別式は一転して凄い雨と風で、これで、もしも雷が鳴ったら平さんが演じた『リア王』そのものだな、とも感じました。
−そうですね。私も、訃報を知った時は耳を疑いました。まるで、「メディア」が幕切れに宙へ飛び去るように、我々の眼の前から姿を消されてしまいましたからね。ただ、その代わりに、多くの皆さんに「想い出」を残してくださったのだと思います。
今日はありがとうございました。

「平さんを語る眼差しに、優しさが漂う」

「廣田さんの胸には平さんの形見のペンダント。平さんへの想いが、今もここにある」

「平さんの想い出話に花が咲く二人」

「グラスを傾けてくれる『あの人』はもういない…」
【廣田 高志(ひろた・たかし)プロフィール】
愛知県出身、1985年に文学座研究所入所、90年に座員となり、現在に至る。
1988年、江守徹が主演の『マクベス』(南座)で初舞台、以後、89年『春のめざめ』(文学座アトリエ公演)、『チェンジングルーム』(文学座本公演)紀伊國屋ホール、91年『桃花春〜戦の中の青春』(本公演)紀伊國屋ホールなどに出演。
1992年、『タイタス・アンドロニカス』(銀座セゾン劇場)で平幹二朗に出会い、1995年の『オセロー』以来、2016年の『王女メディア』まで、「幹の会」の全作品に出演している。
他にも、1994年『ヴェニスの商人』(松竹)サンシャイン劇場、95年『四谷怪談』(銀座セゾン劇場)、99年『元禄港歌』(明治座) などでも共演。
2017年9月24日から10月9日は東京・サンシャイン劇場で松本幸四郎の『アマデウス』、12月5日〜29日には東京・日生劇場での市村正親の『屋根の上のヴァイオリン弾き』の舞台が控えている。




