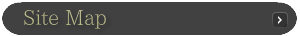第11回 いよいよ「千秋楽」

14:00『王女メディア』(千秋楽)
水戸の2回のステージは、立見席まで含めて見事に完売である。
今回の旅ではこれが最後、と一言の台詞も聞き漏らすまい、と舞台を観ている間に、あっと言う間に芝居が終わる。
習慣的なものだろうが、繰り返して観ているうちに、場面によっては台詞をあらかた覚えている場所がある。芝居を観ながら頭の中に台本が浮かんで来るのは不思議なことだ。
『王女メディア』の幕切れには「救い」も「赦し」もない。
自らの嫉妬の炎で、夫の新しい妻とその父を毒殺したばかりか、最期には我が子を手に掛ける。
しかし、今日のメディアは、すべてを成し遂げた後、どんな過酷な責め苦でも甘んじて受け入れて見せよう、というある種の覚悟に裏打ちされた「崇高さ」が感じられた。
同時に、何かが解き放たれたような、今までよりももう一つ豊かな人間性をも感じられたのだ。
それは、今まで平さんが意識的にセーブしていた感覚を全開にしたからかもしれない。
今までは、様式的になることをあえて避けて演じていたが、その封印を開けたような気がする。
幕切れに至るまでに大きくうねるメディアの感情が、今日はとても生々しく舞台から観客席にぶつかって来た。
こうしたケースが他にもあったことなのか、今日の舞台でそうなったのか、これは平さんに聞かなければわからない。
千秋楽の幕が降りてなお、私の眼の前に宿題ができた。
芝居の楽しみはこういうところにあるのだ。
素晴らしい舞台は何度観ても、必ず新たな発見や感動がある。
だからこそ、観客の要望を受けて回数を重ねることになるのだ。
「土地の女全員」(コロス)の『あるまいか』という最後の台詞の後、一瞬舞台の照明が消える。
しばらくして、大きな拍手が押し寄せた。とても320人分とは思えない。
カーテンコールが繰り返される中、隣の人は立ち上がり、「日本一!」と叫んでいる。
異議なし、まさに日本一のメディアが、わずか10メートルほど先で微笑んでいる。
すべてを走り切ったロングランナーのように。
最後に、舞台の上から紙吹雪が舞ってきた。
これは今回限りのスタッフからの粋なプレゼントだ。
前日の公演終了後に紙吹雪を降らせ、そのスピードや量などを調整していたのだ。
その場に偶然居合わせたが、舞台にはキャストの皆さんはいなかったので、誰もが思わぬプレゼントに喜んでいることだろう。
千秋楽に紙吹雪が花を添えた。
楽屋には大勢のお客様が面会に詰めかけている。
東京から特急で約一時間、今日のために東京から駆け付けた人もいるだろう。
それだけの価値がある舞台だ。
そうした賑わいの傍ら、スタッフたちは昨日と変わらぬテンポで、まるで明日もどこかの地で公演があるように、テキパキと荷出しの準備を進めている。
衣裳さんの部屋を通りかかったら、先ほどまで平さんが着ていたメディアの血まみれの衣裳がハンガーにかかっている。
まさに、96ステージの汗が染み込んだ物だ。
お疲れ様でした。
この衣裳、この後はどうなるんですか?」と伺うと、希望があれば役者さんに差し上げるのだとか。
確かに、毎日のようにその衣裳を着て舞台を演じていた本人に一番の愛着があるのは当然だ。
舞台では、衣裳は「消耗品」の一つになるものもある。
しかし、限りない想いが込められたものでもあり、役者の汗を吸いながら、その苦悩を共にした仲間でもあるのだ。
ふと舞台を覗くと、もう舞台には何も残っていない。
大道具さんの手際の良さに驚くと同時に、つい数十分前までここで繰り広げられていたドラマは夢だったのか、とも思えるような光景だ。
「儚い」という字は「にんべん」に「夢」と書く。
平さんをはじめとする役者たちが、2時間にわたって観客に見せた「夢」は、儚く消え、観客の胸の中に住処を変えた。







 つぎへ
つぎへ 目次に戻る
目次に戻る