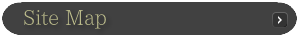「平さん、『王女メディア 一世一代みたび』はいかがですか?」
2018年10月22日
プロデューサー 秋山 佐和子
聞き手:中村 義裕(演劇評論家)

−2018年10月22日は平さんの二回目の命日、「三回忌」に当たります。平さんの命日を前に、「幹の会+リリック」のプロデューサーとして20年にわたり歩みを共にされ、このHPの発案・運営責任者でもある秋山佐和子さんに、「改めて、今『平幹二朗』」を語っていただきました。
−もう三回忌なんて信じられないですね。
秋山 本当に。平さんから電話があったのがつい昨日のことのような気もします。現実には、何もしていないうちにどんどん月日だけが経って行きました。
平さんへの熱い想いが詰まった原稿を多くの方々にお寄せいただいて、こうしてHPも作成しましたが、人の「何か」を残すことの難しさを改めて感じますね。
多くの皆さんがご存じのように、平さんの亡くなり方があまりにも急でしたから、今でも信じられません。平さんが生きていたこと、ひいては自分が今生きていることさえも、すべてが儚い夢なのではないかという感じを持つことがあります。
一周忌を迎える頃に、「これではいけないな」と思いましたが、とは言えそう簡単に割り切れるものでもないですね。まずは、今の自分の「現世」をしっかり生きなくては、と思えるようになったのは、最近のことです。
―そのように気持ちを整理されるまで二年かかった、ということですね。
秋山 そうですね。やはり、この仕事に命を懸けていた平さんと20年間一緒に作品を創ってきたのですから、気持ちを整理するのにそれだけ時間がかかったのだと思います。いまだにここに平さんがいても何の不思議もない、という感覚はあります。それだけ、平さんから人間的に大きな影響を受けていたことが、亡くなって改めてわかりました。
20年も一緒に仕事ができた、ということは、俳優としての魅力はもちろん、仕事に向き合うひたむきで謙虚な姿勢にも魅力を感じていたわけです。
−三回忌を迎えるに当たり、平さんへ呼び掛ける言葉は何でしょうか。
秋山 …まだないですね。もしあったとしても、日常会話の続きのような言葉しか出て来ません。「平さん、少し飲みすぎちゃいましたね」とか、「今までどこにいたんですか、連絡が取れないから心配しましたよ」とか。
−それは、今までに何度となく交わされた言葉で、今も平さんが、秋山さんの傍らにおられるからなのでしょうね。例えば、「天国では今、何のお芝居をしているのですか」などの言葉は、平さんが亡くなったことを認め、受け入れていないと出て来ないと思うのです。
秋山 そうなんでしょうね。もちろん、もう会うことはないわけですが、まだどこかに平さんがいるような気がします。
−私の部屋にも、自分が教えを受けた方々の写真がありますが、亡くなったという感覚はないですね。
都々逸に「夢でなりとも逢いたいものよ 夢じゃ浮き名は立ちはせぬ」というのがありますが、その気持ちが分かるような気がします。もちろん、秋山さんと平さんがそういう関係でいらしたという意味ではありませんが(笑)。
秋山 いつも聞こえてくるのは、「電話くれた?」という平さんの声ですね。私が掛けて、出られなかった時の折り返しの第一声。あと、「おざす」って。これは、向こうから掛かって来た時で、私が「おはようございます」って言うから、おうむ返しに仕方なくという感じで。早く用件を話したくてウズウズしているんです(笑)。その二つの言葉が今でも耳に残っています。
やはり、私は平さんに対して未練があるんですね。『王女メディア』で、全てをやり切ったという想いがあれば、淋しいけれど、納得して見送ることが出来たのでしょうが、仕事として、出来なかったことに対する後悔と未練、でしょうね。平さんご自身も、年齢や肉体のこともあり、ここ数年は「自分の締めくくりをどうするか」を考えておられたと思います。
−そのお気持ちはよくわかります。もしも、他の方だったら20年という長い歳月を、それほどの信頼では結ばれなかったのではないでしょうか。
秋山 平さんの気持ちを理解しよう、寄り添おうという気持ちが大前提にあり、それが少しでも平さんの俳優人生の助けになっていたと思えれば嬉しいですね。
−平さんも信頼がおける相手だったのですね。こちらから観ていると、秋山さんは大きな事は大胆に判断される代わりに、小さな事には迷われる場合があるように思えます。平さんもそういった感じがありますね。それも、コンビがうまく行っていた理由ではないでしょうか。
秋山 それはあったかもしれませんね。それから『外柔内剛型』のところはそっくりだと思います。二人とも簡単には諦めませんし。また、自分が知らないことには謙虚にお互い向かい合って来ました。
平さんはシャイで遠慮深い方でしたから、口には出さない想いを汲み取る必要がありました。その想いは出来る限り汲み取って差し上げて来たつもりですが、最後の想いだけはそれが出来なかったという後悔はあります。
−役者とプロデューサーの信頼感ですね。
秋山 何かで失敗すると、「頼みますよ〜、プロデューサー!」というような言い方をされましたけれど、怒っているわけではないんです。私のことを「プロデューサーとして認めているんだよ!」という優しい励ましの言葉に聞こえました。だからこの言葉を聞いた時は、いつも嬉しかったです。本当に怒った時は、「僕は命を懸けてやってるんだよ!だから君も命を懸けて!」という言葉に変わりましたから。
これは、なかなか一般の方にはわかりにくいことかもしれませんが、旅公演の「芝居」「移動」の繰り返しの生活の中では、「食事」の楽しみが占める比重が普段以上に大きくなります。場合によっては夜の芝居を終えた後、次の公演地までの移動のバスの中で、お弁当で夕食をすませなければならない場合もありますしね。
私が仕事で東京にいた時に、旅先での食事がとてもお粗末だった日がありました。平さんは「幹の会」の主催者として、他のメンバーに気を遣って追加のオーダーもしたようですが、それでも満足の行くものではなかったらしくて。芝居が終わってから夜の食事になりますから、地方によっては遅くまでやっているお店も少ないんです。そういう状況で、深夜に電話があり、繰り返し何度も叱られました。私は「申し訳ありません」と繰り返すばかりでしたが、平さんの怒りは収まりませんでした。会話の途中で、「僕、一人だったんだよ…」と悲しそうにおっしゃった平さんの言葉に、私は、プロデューサーとしてその場に居合わせなかったことを心から申し訳なく思いました。「申し訳ありません」という心からのお詫びが通じた時に、平さんは「じゃあね」とあっさり電話を切りました。こちらの気持ちが伝われば納得していただけるし、うわべの言葉で謝ったりお詫びをしても、すぐに見破られてしまうのですね。これは、芝居の演技と一緒なのでしょう。
−いろいろな想い出を残してくださっても、携帯電話の連絡先に「つながらない相手」がだんだん増えて行きますね。
秋山 そうですね。私は亡くなった方の電話番号は一人も消していません。名前を見た時に、パッと思い出せますから。以前、一年前に亡くなった方の奥様からお電話をいただいたことがあります。でも携帯電話の表示はその方の名前ですから、一瞬「ドキッ」としました。奥様も、ご主人が亡くなられても携帯電話を解約はしないでおられた、ということですよね。ご主人の仕事の電話連絡もあったのかもしれませんが、やはりなかなか消す気持ちにはならないのでしょうね。
―どなたでもそうでしょうが、今までに、年齢、性別に関係なく、大切な方をたくさん喪い、哀しみを重ねながらの歳月なのですね。
秋山 えぇ。多くの方が亡くなってしまいましたが、私が教えを乞い、学んできた方々という意味で考えると、お芝居の世界では、舞台美術家の金森馨(かなもり・かおる)さん、同じく舞台美術家の朝倉摂(あさくら・せつ)さん、劇団四季の浅利慶太さんですね。お元気なのは脚本・演出家の倉本聰さんだけになってしまったのが残念ですが、やはり「特別な方」ですね。
−どういう部分が「特別」だったのでしょうか。
秋山 皆さん、「その道一筋」に生きる方でしたね。「一流」と言われる方々は、いろいろなことに手を出さずに、ただ一つの事だけを突き詰めていらしたんですね。もちろん、「役者」、「美術家」などの中で幅を広げてお仕事をされる、ということはあります。でも、一筋の道を全うするには、人生はあまりにも短すぎますね。
その中でも、平さんは「さらに一筋」でした。『冬物語』と『リア王』、『オセロー』はご自分でも演出しましたが、後は「役者」だけに徹した「一筋」の部分が「特別な中の特別」で、それができるのは凄いと思います。平さんご自身、「役者は僕の天職だ。でも、天才ではない。努力を重ねてここまでやって来たんだ」とおっしゃっていました。やりたいこと、やらなければならないことがはっきりとわかっていて、そこに向かって努力をする。もちろん、苦しみも多かったでしょうが、好きなことのための努力ですからね。そういう姿を終始一貫して見せてくれた点でも「特別な存在」ですね。一緒に仕事をしている時よりも、亡くなってからの方が、その「生き方」がどれほどに凄いものだったかを強く感じるようになりました。
そうした中で、これから自分はどうするのか、平さんとしてきた仕事をどうするのか、を考えるようになりました。
最初は、平さんの功績を残したい想いでHPを立ち上げました。舞台は幕が降りた瞬間に消えてしまいますから、その「記録」を残すことで、これから平さんについて知りたい方々や、後に、平さんのことを調べようとされる若い方々に知っていただきたい、という気持ちからです。加えて、HPが多くの方々の平さんの想い出を語れる場所になればいいなぁ、という想いは今でも強いですね。ただ、これからこのHPをどういう形で充実させていくか、大変な仕事ですが正式な記録を残しておかないと、「記憶」はだんだん薄れますし、曖昧になってしまいますからね。
そうしたことを踏まえて、HPは充実を考えながら更新していかなくては、と思っています。
−今までのお話を伺いますと、このHPで描く「役者・平幹二朗」の行き着く先は「人間・平幹二朗」ということになるのでしょうか。その職業は俳優、性格は職業に対して敬虔に努力を重ね、厳しい判断で臨む人間。千変万化な色彩の演技が、多くの人々の記憶に残っている役者。
秋山 そうですね。平さんが生涯を懸けたのは「演じる」ことだけなんです。後輩を育てようなどの気持ちはお持ちではありませんでした。
台本を受け取り、それを覚えて稽古場へ行き、舞台へ上がる、あるいは映画やテレビの現場へ行く、それだけでした。何をしても「役者」へ収斂して行くんですね。これは誰にでもできることではないと思います。
その中で、俳優人生を懸けたものが『王女メディア』だったのではないかと思います。
−今も平さんがお元気だとすると84歳、ということになりますが、その姿を想像できますか。
秋山 それは私自身の生き方にも関わって来ることですね。
役者・平幹二朗とプロデューサーの私とが「今度は何をやろうか?」と二人で相談しながら、歳月を積み重ねて来たわけです。私にとって、この企画を話し合う時間は、まさに夢のような至福のひと時でした。きっと平さんも同じだったと思います。この時間の平さんは、私の知っている中で一番明るく快活な楽しい平さんでした。
もしも、「今の平さん」の姿を考えるのであれば、間違いなく、千秋楽に「初日が開いた」とおっしゃった『王女メディア』の二日目以降の公演に挑んでいる平さんですね。平さんの芝居は、日々、驚くように成長していったと思います。
そういう視点で考えると、平さんの希望だった「韓国で『王女メディア』をやりたい」ということに向けて動くことでしょうね。ただ、海外公演はいろいろ難しい問題がありますし、平さんに簡単に「次はこうしましょうよ」とは言えませんでした。
今まではそんなことはなかったのですが、二年前の春、『王女メディア』が終わった時には、平さんの体力の限界を考えて、三回目についての話をすることをためらう気持ちがありました。私が躊躇する、ということは、平さんから見れば「秋山は、もう次はやる気がないんだな」ということになります。私が「王女メディアみたび」を提案していたら、平さんはご自身の体力の限界に挑戦して「一世一代みたび」をやったと思います。
あの時、三回目の『王女メディア』の準備をしていれば、平さんは亡くならなかったのではないか、とも思います。もちろん、「もしも」の話ですが、メディアが平さんの身体の中に棲み続けるほど心血を注いだ舞台ですからね。次の予定が決まっていれば、お酒も飲み過ぎないようにメディアが止めたでしょうし、体にも気を配って次への準備を進めておられたのではないでしょうか。
−「まだ終わりではない、でも、もう少し時間を掛けたい」という段階では話せなかったんですか。
秋山 今までは、公演中に、すでに次の作品の準備をしていました。でも、最後の『王女メディア』の時はそうではなかったので、平さんも今申し上げたような判断をされたのではないかと思います。お互いに年を重ね、今回も「これが最後だよ」っておっしゃっていたので、私も「やっぱり最後なのかなぁ」と考えてしまう部分もありました。
−「逢魔が時」ではありませんが、何となく隙間が出来た時間・空間に、平さんは向こうへ行かれてしまった、ということでしょうか。
秋山 我々が計り知れない部分で描かれていた筋書き通りだったような気がしています。役者は仕事のオファー、役、台本など、すべてを「待つ」仕事という一面も持っています。いろいろなものを待った結果、そうなったような気がします。
ただ、平さんの身体の中には37年間「メディア」が棲んでいて、「幹の会+リリック」最後の作品として、『王女メディア』を二回にわたって上演しました。だからこそ、「死ぬまでやりたい」とおっしゃったのでしょう。
―水戸の千秋楽で「ようやく初日が出た」と、それまでの様式のメディアを脱皮した平さんがおっしゃいました。その後、仮に三回目があったとして、それを上回る「メディア」を見せられるかどうか、という葛藤は平さんにはなかったのでしょうか。
秋山 全くなかったと思います。「初日」が出た時に、楽屋で「二日目」をやりたいですね、と平さんに言いましたが、平さんも同じ気持ちだったと思います。そういう感情がなければ、それまで自分の中で復活の時を待っていた作品を、新たに苦労を重ねて演じる必要はないでしょう。仮に体力の衰えが出たとしても、今までの様式から脱皮した新しいメディアが、水を得た魚のようになり、今までにはなかった新しい「メディア」を見せてくれたと思います。
「役者は本番が始まったら、どんなことをしても最期までやり遂げる」と平さんはおっしゃっていました。それが「板の上で死ぬ」ということなんですね。平さんは「板の上で死にたい」とおっしゃっていました。
2012年のビデオをご覧になって、「まだやり残したことがあると思ったんだよ」との言葉が、2014年の「ふたたび」になりました。「『放浪記』と言えば森光子」と言われるように、「『王女メディア』と言えば平幹二朗」と言われるようになりたいんだ。男優でこの役を持ち役にする人はいないだろうから、死ぬまでこの作品をやりたいんだ。とおっしゃっていましたから。
―どんなに濃密な関係でも、歳月と共に想い出も風化します。「去る者は日々に疎し」と言いますが、秋山さんの中で平さんは、一生同じ温度や色彩を保つ方なのでしょうね。
秋山 そうですね。長年、仕事を一緒にして来ましたから。仮に、平さんとの20年が、私が20歳から40歳の期間だったら、感じ方も変わっていたでしょうが、自分がある程度の年齢になってから平さんと出会ったことは大きいですね。
―なるほど。その20年間に大きな印象を残し、突然に去って行かれた感情は、簡単には整理できないものかもしれません。
秋山さんは「平さんに選ばれた人」ではないかと思います。「選ばれし者」には、その方にしか味わえない幸福がある代わりに、喪った時の代償が大きいという不幸が裏表のようになっているのかもしれません。
秋山 そうですね。でも、その幸福があるから人生は素晴らしいのではないでしょうか。
これは若い頃の話ですが、舞台美術を志して劇団四季に籍を置いていた頃、教えていただいていた金森さんが亡くなった時もとても悲しく、しばらくは泣いて暮らしていました。とても信頼していましたし、優しくて魅力的な方で、劇団四季の若い人にもずいぶん慕われていました。その時に感じた悲しみや淋しさを、自分でどう解決したかを考えると、金森さんが亡くなっても、遺してくれた舞台美術がありますから、再演の作品で勉強しようと思いました。また、そこで同じように教えていただいた方々の中に、金森さんの「精神」が生きていることもあると思います。
平さんの場合も同じで、平さんは亡くなりましたが、遺してくれたもので勉強できます。演技は舞台美術と違って、その場で消えてなくなりますが、観た人々の心の中にいろいろな想いを残してくれます。また、演じる方々も、共演された方はその時の刺激や勉強が、俳優としての財産になるのではないでしょうか。そうあってほしいですね。
金森さんは病気で大変な想いをされながらも、劇場にベッドを持ち込んで横になりながら、最期の作品になった『エレファント・マン』に挑んでいた姿を見ていますから、その最期を納得せざるを得なかったんでしょうね。
亡くなる一週間前には、私たち劇団四季で舞台美術を志す者たちに、こどもミュージカル「ニッセイ名作劇場」の舞台美術のコンペをしてくださいました。ソファーに横になりながら、提出した作品の講評とアドバイスを一人一人にくださいました。金森さんから私たち舞台美術を志す者たちへの最期の贈り物でした。
平さんはお元気でしたから、そういう場面を目にしていません。
―現在の演劇界を見回すと、80歳以上のベテランの俳優さんたちがなお第一線という状況です。80代半ばの平さんの芝居は、どんなものだったでしょうね。「俳優」の仕事は、表現者が年を重ね、演技に深みを増すとまた違った味わいが出て来ます。それまでには何十年という時間がかかるのですね。
秋山 その長さにも仰天しますが、一生懸命やればやるほど短いな、という気もします。追求すればするほど奥は深いでしょうし、年齢や経験に関係なく、やればやるほど新しい「何か」が出て来るんでしょうね。身体が元気であれば、何歳になっても出来る芝居があるのだと思います。才能がある方は、次に努力するべきこと、やるべき作品が分かるのではないでしょうか。だから、すぐに時が経ってしまい、ひたすらにそれを追求している間に、80歳を超えてしまうのではないか、とも思います。
−それは、平さんが持ち合わせていた「鋭敏で怜悧な感覚」の産物とも言えるのではないでしょうか。
秋山 いくら才能を持っていても、努力をしなければ実は結びませんからね。一つの道に長けた方は、誰に頼まれるわけでもなくて、「やりたい」んでしょうね。
−結果的には、平さんの「王女メディア 一世一代みたび」は叶いませんでしたが、この二年間に「『王女メディア』みたび」について、お考えになりましたか。
秋山 「新しいメディア」を考えられるようになったのは、最近ですね。平さんとの仕事を通して今までの時間を考えると、これからの私の仕事の一つは、平さんがやりたかったことを続けられるような体制づくりなのかもしれません。「『王女メディア』みたび」があるのなら、平さんのように作品を大切にし、慈しんで育てていただける役者さんで上演したいですね。うまく行けば「よたび」「ごたび」と続けられるような…。
それが、プロデューサーとして作品を引き継ぐことなのではないかと考えるようになりました。平さんが積み重ねて来たことを無駄にしないためには、『王女メディア』という作品を生かし続けたいと。
役者が変わっても同じ愛情を持って作品を上演し続けることが、平さんへの供養でもあり恩返しにもなるのではないかと勝手に思っています。それほどの力を、作品自体が持っているのでしょうね。
そして、平さんが初演した『王女メディア』という作品を日本に根付かせることがプロデューサーである私の仕事ではないかと思います。今後、新たな上演の歴史を重ねることが、平さんから始まった『王女メディア』の歴史を紡いでいくことになるのではないかと思います。
−上演を続けることで、作品も活き、「メディア」が観客に改めて刻まれることにもなるわけですね。
秋山 そうですね。ただ、一本の芝居の上演にはクリアしなくてはならない条件がたくさんありますから、「すぐに」というわけには行かないでしょうけれど。「みたび」があるとすれば、当然ですが「平さんの『王女メディア』」とは違う「新しい『王女メディア』」になるわけです。その中に、今までの『王女メディア』の歴史が少しでも感じられる舞台が理想なのかもしれません。
―具体的なイメージはお持ちなのですか?
秋山 まだ、とてもとても。いろいろな役者さんの顔を思い浮かべているところです。中村さんもよくご存じでしょうが、企画を立ち上げて、キャスティングやスタッフィングをして、劇場を押さえて、となると、二年から三年がかりですから。
−平さんの場合は、台詞の修辞が高橋睦郎先生だったことも大きいですね。
秋山 そうなんです。高橋先生の修辞は平さんがメディアを演じることを前提に書かれています。詩的な言葉の美しい感性があり、男優が演じるのに相応しい、力に満ちた言葉になっています。あの台本で演じなければ、「みたび」の意味はないでしょうね。
−「みたび」を実行するには、さまざまな局面での「覚悟」が必要、ということですね。もちろん、経済的な問題もありますね。
秋山 平さんは経済的な問題にも理解が深く、予算の中で作品を創ることが絶対でした。予算がない時は表現したいことを創造力で補い、そのための工夫をも楽しんでもおられるようでした。
それは、お互いに「いい作品」を創りたいという想いを中心にしての20年だったように思います。
−平さんにも秋山さんにも大切な作品である『王女メディア』が、「みたび」として甦ることを、泉下の平さんも望んでおられると思います。一本の芝居を創るのは並大抵の仕事ではありませんが、今も傍らで秋山さんを見守っておられる平さんが、微笑みを湛えて頷いておられるかもしれませんね。
どうか、実現に向けて頑張ってください。
秋山 ありがとうございます。なるべく早く実現できるように、努力します。
合掌




「平 幹二朗さんの三回忌に想う」
演劇評論家 中村 義裕
足しげく劇場へ通うようになり出して40年以上、個人的なお付き合いをいただくようになった演劇人を、いったいどれ程見送ったことだろう。お付き合いの仕方や年月などでは、臨終直後にその枕頭へ駆け付けたり、告別式の前にご自宅へ弔問に伺ったケースもある。
そうした先輩たち、また最近は、先輩だけではないこともある年齢になってしまったことも哀しみの一つだが、舞台で、あるいは楽屋で、時には盃を交わしながら私に見せ、聴かせ、話してくれたものが私の唯一無二の財産である。もちろん、平さんとて例外ではない。最期の旅になった『王女メディア』では東京公演の初日乾杯の席で平さんと話しているうちに感動で一杯になり、その後の東北公演にもお邪魔した。その詳細は、このHPの「旅日記」をご覧いただければ幸いである。水戸で「千秋楽」を迎え、上野までの電車の中で、プロデューサーの秋山さんの計らいで隣の席を取っていただき、交わした会話は今も鮮明だ。「千秋楽に初日が出た」と言うほどの満足感を得ながら、さして興奮していたわけでもなく、淡々と話し、時折、車窓に目をやる沈黙の繰り返しの間に、最後の「旅」は終わった。今思えば、あの時間に、心地よい疲れと静かな興奮に平さんは身を委ね、早くも次の「みたび」に想いを馳せていたのだろうか。
実を言うと、私が平さんと親しく話すようになったのはそう昔のことではなく、この『王女メディア』の旅だ。亡くなる数か月前からのお付き合い、という珍しいケースに当たる。しかも、「演劇評論家」と名乗りながら何ともお恥ずかしいことに、実質的に最期の舞台になった『クレシダ』には個人的な事情で足を運んでいない。しかし、その怠惰な気持ちが、平さんの突然の死、という天から叱られたような結果になった。多くの方がそうかもしれないが、私自身、平さんとの「別れ」にけじめを付けることができぬまま、三回忌を迎えた。
今更のようだが、いろいろな意味での「時」を経て、ようやく平さんへ私なりの「けじめ」を付けなくてはならない。改めて「弔辞」もおかしなものだが、平さんへ出しそびれた「最後の手紙」とでもお感じいただければ幸いである。
弔辞
平さん、東北から水戸の千秋楽までの想い出が、ついこの間のようでもあり、遥か彼方の出来事だったかのようにも思えます。あなたが掻き消すように我々の目前から去られ、二年が経ちました。世の中は相変わらず多くの事件が起きておりますが、すべて天上からご覧なのでしょうから、ご報告はいたしません。ただ、このところ、演劇界の疲弊が日を経るごとに進んでいるように思うのは私だけでしょうか。
我々は生きている以上、自分を筆頭に多くの方々の死が隣り合わせの日々を送っています。いつ、どのような形で自分の生涯を閉じることになるのか、それは神のみぞ知るところが人生の不安でもあり、そのために日々を充実させる動機の一つでもあるのでしょう。
芝居を観、その批評を書くことを生業にしている私にも、多くの観客の方々のように忘れ難い舞台はいくつもあります。残念なことに最近、そうした物が少なくなっているのも事実ですが、あなたが見せてくれた『王女メディア』は、私の中で間違いなくその席を占めています。幕が降りてしまえば、そこには何も残らないのが舞台の魅力であり、儚さでもあります。頭の中でその様子を反芻するしか術はないのですが、その姿はなぜかより色合いを濃くしてゆきます。
平さんが長年の役者人生の中で他の役よりも多くの熱情を注がれた作品がいくつかあるのだとすれば、その中でも『王女メディア』は飛びぬけたものであることは今更申し上げるまでもないことですね。
素晴らしい「メディア役者」を突然に喪ったことは、演劇界にも私個人にも大きな痛手ですが、作品は残っています。いつの日か、誰かが新しい『王女メディア』を創って見せてくれるのでしょう。その日を待つしかないのですが、次の「メディア」が誕生した折に、批評家としてその舞台とどう切り結ぶのか、平さんから大きな宿題をいただいたような気がしています。「『王女メディア』みたび」を、平さんは天上から歯軋りをしながら、あるいは余裕の微笑みを浮かべながらご覧になるのでしょうか。
どうも、まだ「さようなら」とは申し上げられないようです。頭の中で、朗々としたメディアの台詞が響いているうちは。私が次の『王女メディア』とどう闘うのか、それが始まるまでの間、束の間かもしれませんが、安息の眠りをお祈りしています。




 「平幹二朗さんの七回忌に寄せて」
「平幹二朗さんの七回忌に寄せて」