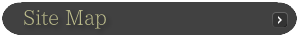2022年10月22日
プロデューサー 秋山 佐和子
演劇評論家 中村 義裕

「平幹二朗さんの七回忌に寄せて」
プロデューサー
リリック 秋山佐和子
この十月二十二日、平さんの七回忌を迎える。平さんの死を悲しみ、惜しみながら、六年が過ぎ去った。
最近ようやく平さんの録画を見ることができるようになって来た。録画を見ると、平さんがどんどん過去の人になっていくような気持ちになり、見ることができなかったのだと思う。心の中で生きていて欲しいと願っていたのかもしれない。
しかし、そうも言っていられなくなって来た。私には平さんの仕事を次の若い世代に橋渡ししなければならない務めがあるからだ。
「平さんはコロナ禍をどう受け止めていただろう?」と私はよく想像する。
あるインタビューで、「僕は何でも受け入れる性格なのかもしれない。もしかしたら戦争で大変な時期に少年時代を過ごしたことが影響しているのかな」と答えていた。
この言葉から、打ち続く舞台の休演を憂いながらも、コロナが収束するであろう時のために、日々黙々と精魂込めて、舞台に備えての鍛錬に励み続けていたに違いないと思える。辛い状況の中でも孤独になり、自分を深化させることが大好きな人だった。
それにしても、コロナ禍に巡り合わずに舞台人生を思う存分全うできた平さんは、本当に幸せな演劇人だったと思う。
私の心に深く印象に残っている平さんのエピソードを幾つかご紹介したいと思う。
これらのエピソードを読んで頂ければ、平幹二朗という舞台俳優の片鱗が次代の演劇を担う若い人達に少し知って頂けると思う。
★僕は平幹二朗
平さんは、あるインタビューで自分のことをこう語っていた。「普段はボーッと生きています。舞台で演じている時、初めて自分の名前は平幹二朗です、と言えるんですよ」
これは単に自分の仕事が舞台俳優だから、ということではない。
「僕は自分の言葉で内面を外に出すことができません。そこに役という仮面があると、自分の内面が自由に動き出すんです。仮面があることで安心して、悪い衝動や毒々しい衝動、悲しみなど、そういうもの全てがマグマのように噴き出してくるんです」
★「王女メディア」の初日が出た日
一九七八年(蜷川幸雄演出)の初演以降、四五〇回近く上演した『王女メディア』。蜷川演出では上手く表現できなかったメディアの心を演じたいという想いから、二〇一二年、高瀬久男演出による新しい『王女メディア』を上演した。そして更に、メディアのもっとリアルな心を表現したいと再演を重ねた。
その再演の二〇一六年の大千秋楽の終演後の楽屋で、「やっと初日が出たよ」と平さんは高揚しながら嬉しそうに言った。その笑顔が忘れられない。初演以来、世紀を超えて担っていた重荷を下ろした清々しい穏やかな笑顔だった。
三十八年かけて、四五〇回上演して初日が出たと言った舞台俳優は平さんしか知らない。
★舌が覚えていた
劇団四季の『ベニスの商人』でシャイロックを演じた時のこと。終幕二十分間に及んだ、食当たりの腹痛との格闘を再現しながら話してくれた。
周囲の人々から蹴飛ばされ、罵倒される場面を二十分間、とにかく喋りに喋り続けた。自分では何を喋っていたのか全然分からなかったそうだ。「もう少しお手柔らかに」と必死に頼んだが、誰も気が付いてはくれなかった。
「自分でも驚いたんだけど、膨大な台詞を全部正確に喋っていたんだよ。舌が全部覚えていたんだよね」そして「舞台人生の中で、一番苦しかったよ。粗相したら僕はもう二度と舞台に立てないだろうから、とにかく死に物狂いで頑張ったよ」とお茶目に笑った。
★役作り
稽古初日は顔合わせと本読みをする。
テーブルに座ったまま台本を読むので、稽古着には着替えない。皆さん少し小綺麗な装いでやって来ることが多い。
『リア王』の平さんの稽古初日の出立ちは、幾つもシミのついた薄汚れた白いジーパン、水色のヨレヨレのTシャツ姿だった。この格好で電車に乗ってやって来たのか。リアの役柄作りのために、特別に汚れた普段着を選んで着て来たのだ。
★プロデューサー 平幹二朗
平さんと私、二人がプロデューサーになる時がある。それはキャスティングの時だ。
役どころに合うと思う役者さんをお互いに挙げ、その方について語る平さんのブラックユーモアを交えた語り口が可笑しく、私はいつも笑い通しだった。平さんも我ながら可笑しかったのだろう、いつも笑い通しだった。二人にとってキャスティングは無限に夢のある楽しい時間だった。
★八十才とは思えない声
平さんの声は舞台上は勿論のこと、普段の喋り声もよく響いて通る。広い稽古場の隅からポソッと私の名前を呼んでも、平さんの声は空気の振動に乗って聴こえる。普段の会話も腹式呼吸で喋っていたからなのだ。
その平さんの声が、二〇一二年の『王女メディア』の稽古場での最終稽古の日にまったく出なくなった。平さんがパントマイムの演技をして、プロンプターが台詞を喋るという前代未聞の通し稽古になった。
稽古終了後、平さんは劇団四季の浅利慶太さんから耳鼻咽喉科の先生を紹介していただき、駆け込んだ。初日を予定通り開けるのは無理だろうという先生の判断で、翌日の劇場仕込みは、とりあえあえず一日延期した。
その仕込みの日の午後に、平さんから電話がかかって来た。電話の向こうから「奇跡が起きたんだよ!声が出るようになったんだよ!」と狂喜乱舞の声。こんなに嬉しい喜び、悲鳴にも近い平さんの声を聞いたのは初めてだった。耳鼻咽喉科の先生曰く「八十才の喉とは、とても思えない」だった。
舞台稽古の朝、劇中で使う平さんの声を録音した。一発でOKだった。舞台稽古が一日短くなっただけで、無事に初日を開けて一〇〇ステージの公演を乗り切った。
これからの演劇界を担う若者たちは、だんだん平幹二朗という舞台俳優を知らない世代になる。このホームページはそういう世代の若者たちに、平さんがどのような舞台俳優だったかを残したい、という思いから作り始めた。
終わりの見えないコロナ禍で演劇が疲弊していく中、このホームページも暫く休んでしまったが、平さんの生の記録を残しておくことは、これからの日本の演劇界には貴重だと思い直した。
平さんがライフワークとして一番大切にしていたのが「幹の会」の創作活動で、『冬物語』『リア王』『オセロー』の三作品は演出も手掛けた。
平さんは舞台の面白さについて、こう語る。「演じたそばから消えていく。その儚さに面白さがあるんじゃないかと思う。だから次を求める気持ちが強くなる」と。
平さんも私も、三十八年越しに初日が開いた『王女メディア』を次は韓国で上演したかった。韓国公演の企画が決まっていたら、あの日に命を落とすようなことはなかっただろう。もう少し早く企画を立てていれば良かった、と悔やまれてならない。
コロナ禍の中、平さんは韓国公演に夢を馳せながら、日々黙々と精魂こめて、上演の準備に励んでいるに違いない。
「平さん 七回忌に寄せて」
演劇評論家 中村 義裕
十月二十二日は、平幹二朗さんの七回忌である。これは仏式の数え方だから、亡くなって丸六年、ご存命なら十一月二十一日の誕生日には八十九歳になる。「もう六年も経ったとは思えない」というのが正直な感想だ。平さんが亡くなる数か月前まで平さんと対話をしながら出版の話を進めていたこと、亡くなってから立ち上げたHPの運営に関わり、平さんのことを語り、ゆかりの深い方々のお話を伺い、自身でも想い出を書きもしており、まだ平さんがその辺りにおられるような感覚が残っていたからだ。
「人は二度死ぬ」と言う。最初は肉体の死、やがて、その人の想い出を誰も語ることがなくなり、完全に忘れ去られた時が二回目の死、だと。そういう意味で言えば、平さんの肉体は滅びてしまったが、まだ「二度目の死」を迎えたわけではない。こうして、七回忌を偲ぶ原稿を書き、それを読んで平さんの在りし日の姿に想いを馳せてくださる方もいるからだ。
その一方で、残酷な歳月は、生の平さんの舞台を観たことがない、という人をどんどん増やしている。これは、平さんに限ったことではない。いかなる名優も時の流れには抗うことができないことを、残された立場で痛感している。ただ、「演劇評論家」を標榜する以上、その時々に観た舞台の批評や記録はもちろん大事だが、自分が観て来た名優たちの舞台を、まだ見ぬ若い世代に伝える「語り部」のような仕事も役目の一つだと考えている。平さんの場合で言えば、すべてではないものの四十年以上にわたって舞台を観ている。今はまだその気持ちにはなれないが、いつか「俳優・平幹二朗論」を残すことも、次の世代へ「演劇」のバトンを渡す仕事の一つだと考えている。
平さんが亡くなって以降、2020年2月辺りから「コロナ禍」に見舞われ、演劇界はその形を変えざるを得ないほどのダメージを受け、現在もそれは続いている。いつの日か「収束」と言われた時に、それ以前の演劇界とは全くありようの変わってしまった姿を、平さんなら何と言うだろうか? ある意味では、この寂寞とした荒涼たる世界で自分が何をすべきかに悩むことがなかった平さんは幸せだったのではないか、とも思える。
この六年の間に、「コロナ禍」の影響を受けて演劇界から去った方もいれば、鬼籍に入られた方もいる。平さんが共演し、信頼していた若松武史さん。最期の『王女メディア』の巡演でもご一緒したが、既にあまり体調が良さそうではなく心配だった。しかし、舞台では微塵も不調を感じさせることなく、俳優として叩きあげた力を見せてくださった。2002年から翌年にかけての『リア王』、2004年の『オイディプス』に出演されていた藤木孝さん。若松さんからは旅公演の合間に喫茶店などでお話を伺い、藤木さんにはこのHPで平さんの想い出を語っていただいた。そうした事どもの数々が「想い出」として積み重なってゆくのは何とも残酷な話だ。
「演じる」ための技術は、DVDの記録映像などを見ればある程度のことはわかるだろう。しかし、よく言われるように、「あくまでも記録であり、肝心の『芸』は映らない」。だからこそ、俳優は全身を駆使して、作品の内容や人物の感情を表現するために藻掻き苦しむ。一生を懸けて追求を続ける俳優の『芸』の形やありようを具体的に提示することはできない。しかし、肉体のすべてを使って表現する「精神性」、そこに至るまでのプロセスなどを、幸いにも平さんの肉声で聴くことができた。これは、平さんが私に遺してくれた形見でもあり、財産だとも思っている。長いお付き合いではなかったが、その分密度は濃かったのではないか、と勝手に思っている。
平さんが亡くなって六年、その分、年齢の差は縮まった。私の半生には、肉親に限らず自分が関わった方々が亡くなった年齢が墓標のように並んでいる。中には、その年齢を過ぎてしまった方もいれば、平さんのようにその年に年々近付いて行く方もいる。
六年の間で何か学んだことがあるとすれば、平さんが舞台の幕が開く前の稽古などを含めたプロセスは見せたくない、と言っていた気持ちが少し実感として分かるようになったことだろうか。これを私自身の老いと考えるのか、いくらか人間が成長したのだと考えるのか。結論は出す必要はないだろう。ただ、こうして亡き人に想いを馳せることが決して無意味ではなく、まだ学べることがあるのは事実だ。
私の手元には文字になっていない物も含めて、平さんとの対話が十時間以上残されている。ただ、まだそれを文字に起こす気持ちにはなれずにいる。いつ、どういう形かは分からないが、いずれ皆さんにお目に掛けなくてはならないとは考えている。しかし、それを終えてしまうと、平さんとの仕事が本当に終わってしまったのだと感じざるを得ないだろう。恐らく、それが嫌で逡巡しているのだと思う。もうしばらく躊躇っていることになるのだろう。平さんに聞けるとすれば、何と答えてくれるのだろうか。無言でニヤリと笑うだろうか。








 「平幹二朗さんの三回忌に寄せて」
「平幹二朗さんの三回忌に寄せて」