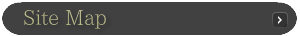第10回 「千秋楽」の開演前に

3月6日(日)
いよいよ千秋楽。9月から始まった旅も、今日で終わりを告げる。
11:00 ホテルにて
喫茶室にて、「女たちの頭」を演じているベテラン・若松武史さんの話を伺う。
大小の舞台に関わらず、ずいぶん若松さんの芝居を観て来たが、今回は特に若松さんに聞きたいことがあり、千秋楽の楽屋入り前という貴重な時間を割いていただいたのだ。
それは、平さんと若松さんでは「役者として歩いて来た道筋が全く違う」ことだ。
どんな道筋を歩いて来ようが、舞台の上がすべてだが、若松さんがどういう眼で平さんを見ているのか、それが知りたかったのだ。
平さんの役者としてのスタートが新劇の老舗「俳優座」であったのに対し、若松さんは1974年に寺山修司が率いる『演劇実験室◎天井桟敷』で俳優としての歩みをスタートし、83年まで中心的な俳優として活躍している。
いわゆる「アングラ」と呼ばれる芝居だ。
83年に寺山が没して以降は、商業演劇や映像にも活躍の幅を広げ、美輪明宏の『毛皮のマリー』や山本一力の『あかね空』など、作品の幅も広い。
平さんとの共演は『NINAGAWA マクベス』や『王女メディア』などだが、こうした長い旅公演は初めてだ、とのこと。
芸歴40年を超える若松さんから見ても、平さんの凄まじいパワーと、前のめりで進んでゆく貪欲さには圧倒されるようだ。
「平さんは若い頃からの憧れでしたね。あれだけの集中力を持つ役者は、そうはいません。念願かなって初めて共演したのが、1987年に蜷川さんが演出した『テンペスト』でした。今もですが圧倒的なエネルギーの持ち主でしたね。
それと、平さんは肉体的にも精神的にも僕らの言葉で言う「開いた状態」なんです。そこで、相手のエネルギーを吸収してから放出する。その時には、エネルギーが何倍にもなっているんです。こっちもそれを受けて返す、の繰り返しの相乗効果で、芝居が良くなる場面があります」
若松さんの「感覚的な」言葉の端々に、寺山修司という天才と仕事を共有した実感がある。「開いた状態」を私なりに解釈すれば、ストレスが少なく、フラットにいられる、ということだろうか。しかし、それも長年の経験のなせる技だ。
「チャップリンも言いましたが、芝居をしている時に、舞台にいる自分を劇場の上の方から俯瞰的に眺めている「もう一人の自分」がいなくてはならない、と。客観的に芝居をしろ、ということでしょうが、平さんにもそれを感じますね。どこかでもう一人の平さんが、客観的に舞台を俯瞰しているような…」。
これは偶然の一致ではなく、私の知る俳優の中で、「名優」と呼ばれる人の多くからこのエピソードを聴く。舞台に立った経験のある人でなければわからない感覚だろう。
「エネルギーが凄いし、まさに『怪物』ですよ」。と語る若松さんは、『王女メディア』を終えると、間を置かずに美輪明宏さん主演の『毛皮のマリー』の稽古が待っているとのこと。
この作品は、寺山修司が美輪明宏のために書き下ろした作品で、こちらも回を重ねて上演し、若松さんは常連だ。
「『怪物』二連発ですね」と言ったら、若松さんが苦笑した。こうして共演者やスタッフの話を伺うと、みんな本当に芝居が好きなのだ、と改めて感じる。
こんなことを書くのは、最近は演劇界にもサラリーマン化の波が押し寄せ、本当に芝居が好きでこの世界に身を投じたのかどうか、というような場面に出くわすことがしばしばあるからだ。
効率から言えば、こんなに効率の悪い仕事はあまりないだろう。
たとえ数日間のステージでも、その数倍の期間を稽古に充て、稽古までには台詞を覚え、役のイメージを創る作業を行わなくてはならない。
経済的に恵まれない場合が多くても、観客に感動を与えられる舞台を求め、誰もが厳しい条件の中で仕事をしている。
しかも、それだけの苦労をしても、作品は幕が降りた瞬間に雲散霧消する。後は観客の胸の中に想い出が刻まれるだけだ。
そこに価値を見出し、その『瞬間』に命を賭けることができるかどうか、それが芝居者の条件なのでは、と若松さんの話を聴いて感じた。




 つぎへ
つぎへ 目次に戻る
目次に戻る