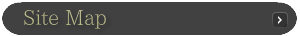小論「平 幹二朗」
演劇評論家 中村 義裕
【想い出の舞台】

演劇評論家として、平幹二朗の想い出の舞台を挙げよと言われたら、順不同と断りを入れた上で、『近松心中物語−それは恋』、『タンゴ、冬の終わりに』、『王女メディア』を三絶とし、『リア王』と『鹿鳴館』を加えてベスト5、としたいところだ。『王女メディア』については別に述べたのでここでは触れないが、いずれも甲乙つけがたい印象を残した舞台ばかりだ。『近松心中物語−それは恋』で帝国劇場を埋めんばかりに降りしきる雪の中、死んでゆく哀しみは、鮮烈だった。また、『リア王』でどんどん孤独が募る老いた王の姿は、現代の世相に通底する部分も多い。『鹿鳴館』ではシニカルな一面をたっぷりと見せた上での緩急自在の台詞術が忘れがたい。『タンゴ、冬の終わりに』は、作者の劇的世界を見事に表現したとの印象がある。
こうして並べてみると、平幹二朗の作品に対する「眼の良さ」がよくわかる。『王女メディア』『リア王』は西欧の古典劇であり、『タンゴ、冬の終わりに』は清水邦夫、『鹿鳴館』は三島由紀夫、『近松心中』は秋元松代と、昭和の演劇史に燦然とその名を残した劇作家の作品ばかりだ。どんな名優でも、演じる脚本が悪ければ、その力を発揮することはできない。二次元の世界で描かれた脚本を、演出家や共演者と稽古場で三次元の形に変え、自らの肉体で観客に伝えるのが役者の仕事だ。その根本である脚本を見極める「眼」を持っている、というのが、優れた作品に出会えることにつながったのだ。
観客それぞれに、「私のベスト」は違うだろうし、当然だ。しかし、どの舞台にも共通に言えるのは、幕が降りた瞬間に、今までの感動も喜びも雲が晴れるように消え、後は観客の心の中に『想い出』として残ることだ。そこが「ライブ感」ゆえの舞台の魅力である。そうした舞台を一本でも心の中に持てることは、観客にとっても幸福なことだ。私は、むやみやたらと「一期一会」という言葉を使うのは好きではない。人生におけるすべての事柄が「一期一会」だからだ。人や書籍、舞台や音楽、仕事や旅、すべてが同じ状況で再現することはできない。人生だけはコピーもクローンも不可能なのだ。そんな人生の中で、平幹二朗の舞台に出会え、それを良き想い出として心の中に持てたことは幸せなことだ。
もしも、平幹二朗本人に、『想い出の舞台は何ですか?』と聞いたら、チャップリンよろしく茶目っ気たっぷりに『ネクスト・ワン』と答えただろうか。それとも、千秋楽に『初日が出ましたよ』と言った『王女メディア』の名が挙がるだろうか。私なりの想像はつくものの、直接その言葉を聴くことができなかったのは、痛恨、としか言葉がない。
(了)

 演劇評論家 中村 義裕
演劇評論家 中村 義裕
目次
【出会い】
【『近松心中物語』のこと】
【平幹二朗の魅力−台詞】
【平幹二朗の魅力―愛称】
【平幹二朗の魅力-風格】
【平幹二朗の魅了-空間】
【三人の演出家】
【平幹二朗と「幹の会」】
【想い出の舞台】