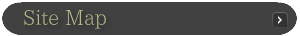小論「平 幹二朗」
演劇評論家 中村 義裕
【平幹二朗の魅力-台詞】

役者の魅力を語る時に、何を一番に挙げるかは頭を痛める問題だ。平幹二朗の場合はその台詞術の見事さ、朗々とした声の良さだろう。江戸の昔以来、役者の魅力を評して「一声二顔三姿」と言う。これに当てはまるケースばかりでもないだろうが、「声」の中にはむろん「台詞」が含まれている。
台詞術は「エロキューション」とも呼ばれ、台詞を活かすも殺すもこれ次第だ。同じ台詞でも俳優によって心に響く、響かないの差が生じるのも、この能力によるものだ。平幹二朗は、抜群の台詞術を持つことで知られている。
芝居を演じるには、自分の役の気持ちを掴み、その気持ちを台詞に乗せて発声することから始まる。演じる役により、あるいは一本の芝居の中でも場面や心理に応じて台詞のトーンやインパクトは大きく変わる。それがない俳優や芝居を「一本調子」と批評されることがあるからも判るように、芝居の中のどこにポイントを置き、さらに細かく言えば一言の台詞の中のどこに急所を見出すかが役者の工夫のしどころでもある。抑揚、あるいはメリハリが芝居のポイントと一致すれば、そこでの効果は大きい。
作品によって、江戸時代を舞台にした作品、大人のコメディ、昭和の作品、ギリシャ悲劇など、時代も質も違う。平の芝居で言えば、『近松心中物語』と三島由紀夫の『鹿鳴館』を同じ台詞術で演じることは効果がない。この台詞の語り分けに非常に優れた才能を見せるのが大きな魅力なのだ。「七色の声」とは女優に適した言葉かもしれないが、彼の声は、何色のグラデーションを持っていたのだろうか。もう一つ、これは長年の舞台経験によって鍛えられたものだろうが、小さな囁き声のような台詞が、客席の後方までしっかり届く。これは、簡単なようだが難しく、特に最近は台詞が聞き取りにくい役者が増えた。その中で、貴重な技術、あるいは魅力の一つである。
シニカルな笑みを浮かべて囁くように言う『鹿鳴館』の影山伯爵のような台詞もあれば、我が身を襲う悲劇に身もだえし叫ぶ『王女メディア』のような台詞もある。こうしたものを自由自在に演じ分けられるところに、恵まれた才能に研鑽を重ねたゆえの「年功」があるのだ。
ギリシャ悲劇のように台詞を謳い上げるように喋る場合、これを「朗誦」と呼ぶことがある。台詞術の一つで、朗々たる声で台詞を謳い上げる「朗誦術」に関しても、平幹二朗はたぐいまれな才能を持っている。詳細は別項の『王女メディア旅日記』に譲るが、2015年の9月から2016年3月にかけて約半年間、82歳にして演じた『王女メディア』の見事さは、共演者のすべてを圧倒するものだった。

 演劇評論家 中村 義裕
演劇評論家 中村 義裕
目次
【出会い】
【『近松心中物語』のこと】
【平幹二朗の魅力−台詞】
【平幹二朗の魅力―愛称】
【平幹二朗の魅力-風格】
【平幹二朗の魅了-空間】
【三人の演出家】
【平幹二朗と「幹の会」】
【想い出の舞台】