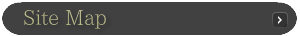小論「平 幹二朗」
演劇評論家 中村 義裕
【平幹二朗と「幹の会」】

平幹二朗の舞台年譜の中に「幹の会」として初めて登場する作品は1995年、62歳の折に栗山民也の演出で演じた『オセロー』である。シェイクスピアの「四大悲劇」の一つとして改めて説明の必要もないほどに有名な芝居だ。なぜ、「幹の会」を立ち上げるに至ったかについてのいきさつは、代表でこのHPの運営責任者でもあるプロデューサーの秋山佐和子氏のインタビューに譲る。以後、亡くなるまで、再演を含めて15回の公演を持っており、特に初期の頃は2002年まで9年続けて、忙しいスケジュールの合間を縫って公演を設けている。

いつだったか、本人が「始めたころ、何となく流れで『シェイクスピアの全作品を上演する』みたいなことを言ってしまって…。やはり、新劇育ちですからね」と語ったが、シェイクスピアが多いのは、その理由が大きいのかもしれない。しかし、他にも代表作の『王女メディア』をはじめ『冬のライオン』、『オイディプス王』、『シラノ・ド・ベルジュラック』などを演じ、珍しいところでは白石瞭の原作・脚本による一人芝居『親鸞/大いなるみ手に抱かれて』と、コツコツとながらも取り上げた作品の幅は広い。
上演記録を眺めてみると、結局は平幹二朗本人が、「望んで演じたかった作品」を取り上げたのが「幹の会」の活動だった、ということだ。その中には好評を受け再演したものもある。「幹の会」の活動は、平幹二朗にとっては舞台人としての拠り所であったに違いない。その証拠は、先々のスケジュールを決める際に、まずは地方の演劇鑑賞会で「いつ」「何を」幹の会として上演するかに心を砕いていた、というエピソードが物語っている。平ほどの売れっ子の俳優が、地方公演を先に決定するところに、その想いが窺える。
別項の「『王女メディア』旅日記」でも述べたが、地方公演は決して楽なものではない。しかし、それをものともせずに自らが演じたい芝居、見せたい芝居に心血を注げる後半生を持てたことは、役者の幸福とは言えないだろうか。こうした想いは、役者である以上多かれ少なかれあるはずで、頼まれる仕事だけを諾々とこなしていても表現者としての喜びは薄いだろう。そのために、自らが中心となって会を結成する役者も多いが、長続きせずに終わってしまうケースが多いのも事実だ。それを、亡くなる年まで続けることができたのは、観客をはじめとする恵まれた環境を持つことができたからだろう。
ある映画監督が私に言ったことがある。「中村さん、自分が本当に言いたいことは、原稿の中に一割あればいいんだよ」と。物書きと俳優を一律に並べることはできないし、名立たる名優と私を一緒にするのは非礼の限りだが、平幹二朗の後半生で、本当にやりたいことは「幹の会」に集約されていたと言っても、あながち間違いではないだろう。
その情熱の傾け方は、何かの折に聞いたプロデューサー・秋山氏の「平さんとは、『幹の会』の初日が無事に開くと、もう次に何をやろうか、という話になっていました。その中で、一番の情熱と愛情を注いでいたのは、やはり『王女メディア』でしょうね。平さんは、「死ぬまで演じ続けたい芝居は『王女メディア』だけ」だと言っていました。これは、今の演劇界では平さんにしかできない舞台ですし、ご本人もやればやるほどそこへ至る想いが強くなったのではないでしょうか」との言葉が裏付けている。ほぼその希望通りになったわけだが、その一方、どの名優が亡くなった折にも感じる「芸も一緒に持って旅立ってしまった」との想いを隠すことはできない。おそらく、ここしばらくは、誰も『王女メディア』を演じることはしないだろう。それほどに、この芝居と平幹二朗とは一体化するところまで到達したのだ。
とは言え、まさか本人も今回の『王女メディア』が幹の会との最期の仕事になるとは思いもしなかっただろう。その長い旅の千秋楽に「ようやく初日が出た気がする」と語った場に居合わせ、肉声を聞くことができた私も幸福だったが、悲劇を演じ続けた役者・平幹二朗の俳優人生は幸せな幕切れを迎えた、と言えるのではなかろうか。


 演劇評論家 中村 義裕
演劇評論家 中村 義裕
目次
【出会い】
【『近松心中物語』のこと】
【平幹二朗の魅力−台詞】
【平幹二朗の魅力―愛称】
【平幹二朗の魅力-風格】
【平幹二朗の魅了-空間】
【三人の演出家】
【平幹二朗と「幹の会」】
【想い出の舞台】