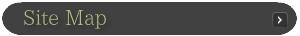小論「平 幹二朗」
演劇評論家 中村 義裕
【出会い】

私が平幹二朗という役者を最初に「観た」のは、テレビ史上に残る名作の一つ、NHK・大河ドラマで1970年に放送された山本周五郎原作の『樅の木は残った』である。当時8歳の私にはその記憶は微かなものでしかなく、当然、「平幹二朗」という名前も後で得た知識だろう。また、この番組はのちに何度も「名場面シリーズ」のような番組で放送されており、それを見るたびに知識が追加されて行ったのが事実というところだろう。

明確に覚えているのは、1978年2月、高校一年生の時に、蜷川幸雄の演出により日生劇場で上演された『王女メディア』だ。アルバイトで得たお金で舞台を観に行く習慣が当たり前になり始めた頃のことだ。人形劇の『新・八犬伝』で大きな話題を呼んだ「ちりめん」を使った辻村寿三郎(当時:ジュサブロー)の衣裳も見事だったが、奇怪とも見えた平幹二朗のメディアには圧倒された。
この舞台にはもう一つ忘れがたい個人的な体験が伴っている。風邪をひいており、8度以上の熱があったのだ。私が持っていた切符はてっぺんに近い席だったが、高校生が2,000円の切符をムダにするのは大変な問題だ。行こうか諦めようかと散々迷った挙句、半ば熱に浮かされたような状態で、日生劇場の天井桟敷に座ったのだ。この舞台の出来栄えと当日の私のコンディションが、『王女メディア』を忘れ難いものにしたのだ。
私は歌舞伎座へものめり込んでいたので、「女形」は知っていた。不思議なことに、このメディアの舞台で、平幹二朗に女形を感じなかった。未熟な頭脳が両者を結び付けられなかったのか、あるいは過剰とも言えるまでの蜷川幸雄のデコラティヴな仕掛けに幻惑されてしまい、そこに想いが至らなかったのか。今となっては、朧の彼方に残された話だが、あえて答えを出す必要もないだろう。一番大きな問題は、私の観劇歴のかなり早い場面から、「平幹二朗」なる役者がその記憶に鮮烈な印象を刻み付けていたことだ。
【『近松心中物語』のこと】
『王女メディア』での鮮烈なショック以降、多くの舞台に接することになるが、不思議なことに平幹二朗にとってはあまり記憶に留めておきたくはないであろう場面にも出会っている。怪我や病気による降板だ。例えば、1979年、秋元松代(1911~2001)が渾身とも言える筆致を見せた『近松心中物語』の初演だ。これは、劇作家・秋元松代にとっても記念碑的な作品でそれまではいわゆる「新劇」に優れた作品を提供していた作家が、大劇場演劇に初めて書き下ろした作品である。その後、『元禄港歌』、『南北恋物語』と大劇場作品が続くが、彼女が大劇場に残した作品は、『近松心中物語』が一番優れたものだ、というのは衆目の一致するところだろう。
加えて、蜷川幸雄が幕開きの群衆を巧みに捌いて見せるシーンや大詰めの雪の中での美しい心中が話題になったが、何よりも、平幹二朗と太地喜和子のカップルが見せた色気と情愛、哀感は絶妙としか言いようがないものだった。以来、多くのカップルがこの役を演じているが、この役ばかりは初演の二人に尽きるとも言える。
現在までに上演回数が1,000回を超えているこの作品は、江戸時代の浄瑠璃作者で「心中物」のパイオニアとも言うべき近松門左衛門の『冥途の飛脚』を基本に据え、『ひぢりめん卯月の紅葉』『跡追心中卯月のいろあげ』をアレンジして書き加えた二組の男女の物語だ。1979年の2月から2ヶ月にわたり平幹二朗、太地喜和子のコンビに、山岡久乃、金田龍之介、市原悦子、緋多景子、菅野菜保之(当時は菅野忠彦)らの豪華なメンバーで初演された。
これは東宝が相当に力を入れた舞台であったことがよくわかる。いわゆる大劇場演劇の顔ぶれとしても腕達者を揃えたばかりか、当時の東宝の舞台で『屋根の上のヴァイオリン弾き』のように評価が確立した作品以外でいきなり2ヶ月公演というのは大英断だったはずだ。しかし、この賭けは東宝が見事な勝ちを収め、多くの観客が二人の心中に涙した。「賭け」とは不遜な言い方に聞こえるかもしれないが、「舞台は水物」と言われるように、どんなに素晴らしいメンバーを揃えた作品でも、観客が入らないことは珍しくない。この舞台は、作品がしっかり作り込まれていた上に、気鋭の蜷川幸雄の演出、平幹二朗・太地喜和子の二大スターの共演と、話題になることはいくらでもあった。
しかし、「好事魔多し」と言う。公演中にアクシデントが起きた。主演の平幹二朗が腰を痛めてやむなく降板、という事態が起きた。役者が舞台を降板するのは何よりも辛いことだ。しかし、翌日以降も幕を開けるためには、コンディションを一番よく把握している自分自身でジャッジをくださなくてはならない。恐らく、人には言えないほどの苦しい決断を経て降板を決意したことは想像に難くない。自分の問題もさることながら、観客や共演者、スタッフに与える影響の大きさは役によっては計り知れない。まして、主役の降板となれば代役の問題も含めて、即座に解決しなくてはならない問題が一気に山積みになる。
私も、数年間劇場でアルバイトをしていた学生時代に、主役が初日に体調不良で降板という経験をしており、その事態がいかに重大な問題かを実体験したことがある。
平が腰を痛めて降板した折、彼の役である忠兵衛の台詞を全部覚えていて、代役に抜擢されたのが本田博太郎だった。代役で思わぬチャンスを得て出世の糸口をつかむ役者は江戸時代以来多数いるが、この時の本田博太郎の出現はある種のインパクトを与えた。
私はこの公演を二回観ている。最初は平が忠兵衛を演じた折、二度目は、偶然にも本田博太郎の代役の初日だった。話題の舞台で評価も高かっただけに、当時46歳の平がどんな気持ちでこの舞台の降板を決意したか。役者であれば可能性は誰にもあることだが、私にも朧ろげではあるが判るような気がする。
腰の治療が終わった後、この降板のショックを取り返すかのように、2年後の1981年には11月、12月と再度2ヶ月の公演を勤め、翌82年4月には名古屋・御園座(2017年1月現在、建替のため休館中)、83年5月には大阪・道頓堀の朝日座(84年に閉場)、8月~9月には再度帝国劇場、85年12月には御園座での再演、86年3月には大阪・近鉄劇場で大阪での再演をしている。その後、2001年には1月~2月に大阪・近鉄劇場、3月~4月に東京・明治座で上演し、実に9公演にわたり、初演以来22年の歳月を費やして演じる作品となった。
どんなに素晴らしい内容の作品でも、観客の求めがなければ上演は叶わない。まして、回を重ねれば重ねるほど、観客の期待は高まり、ハードルは上がる。また、公演により相手役や周囲の役が代わり、いつも同じ芝居ですむわけではない。それらを乗り越えながら、22年にわたり大都市の大きな劇場でこの作品を大切に演じて来たことに、平幹二朗という役者の想いが感じられる。

 演劇評論家 中村 義裕
演劇評論家 中村 義裕
目次
【出会い】
【『近松心中物語』のこと】
【平幹二朗の魅力−台詞】
【平幹二朗の魅力―愛称】
【平幹二朗の魅力-風格】
【平幹二朗の魅了-空間】
【三人の演出家】
【平幹二朗と「幹の会」】
【想い出の舞台】