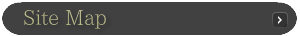小論「平 幹二朗」
演劇評論家 中村 義裕
【三人の演出家】

役者の芝居を生かすも殺すも演出家次第、という。詳細はHPの年譜にゆずるが、平幹二朗が大きな足跡を遺すことができたのは、三人の演出家との出会いが大きな役割を果たしている。生涯に一人でも影響を受ける演出家に出会えれば、役者の幸福だ。それが、三人の、カラーの違う演出家と時代を共にしていることは、役者・平幹二朗を造る上での大きな要因になったことは間違いない。
俳優座の創立メンバーの一人で、自らも俳優として舞台に立った千田是也(1904~1994)、劇団四季の創立者である浅利慶太(1933~)、奇しくも同じ年に鬼籍に入った蜷川幸雄(1935~2016)。
今はもう「千田是也」という名前は、演劇界の人々にも遠い名前になってしまった。しかし、その演出技法や遺した仕事は今も演劇界に残されている。千田是也が「俳優」として舞台に立った期間はそう長くはなく、演出に専念することになったのも遠くなってしまった理由の一つだ。しかし、その現役時代に平幹二朗は共演を果たしている。今のベテランの俳優の中で、千田演出を受けた経験のある人は少ないながらも活躍中だが、共演の経験があるという人はほとんどいないだろう。
平幹二朗の俳優人生の起点となった「俳優座」は、「老舗の三大劇団」として文学座、劇団民藝と並び称され、1944年に東野英治郎、小沢栄太郎、青山杉作、千田是也たちが創立した劇団である。現在も六本木の交差点そばに、自前の「俳優座劇場」を持ち、定期的に公演を続けている。1956年、劇団が設けていた俳優座養成所の研究生となった時点から、その俳優人生がスタートを切った。俳優座には11年の在籍を経て退団することになるが、俳優としての基礎教育をこの劇団で受けられたことは、俳優・平幹二朗の最初の幸福であった、と言うべきだろう。
当然ながら、私はこの当時の平幹二朗の舞台は知らない。また、今の姿から当時の平青年の芝居がどのような雰囲気を持つ役者だったかは想像しにくい。当時の劇界をよく知り、俳優座にも在籍の経験があり、のちに青年座の設立に関わった同年代の演出家・川和孝氏(1932~)に若き日の「平幹二朗」の印象を伺った。
「あの当時、言い方は悪いけれど新劇の劇団なんていうのは、みんな何だか思い詰めたような暗い顔で、背中を丸めて何か物思いに耽っているような感じの若者ばかりだったような印象がありました。
そこへ彼が登場したのですが、立派な体格を持ち、「陽性」の演技や行動が非常に新鮮な存在として目立ちましたね。今までの新劇人が持っていた物とは明らかに違う「何か」を持った人なのだと感じましたね」。
この川和氏の感覚は卓見であると同時に、その後の平幹二朗の方向性を予見していたとも言える。本人にこの当時のイメージを語ってもらってもこうした言葉は出て来ない。客観的な意見だからこそ評価したいのだ。
1966年、33歳の時に、平幹二朗は劇団四季の舞台『アンドロマック』で二人目の演出家・浅利慶太に出会う。その後、68年まで俳優座・劇団四季の舞台を行き来しながら、劇団四季で『アンチゴーヌ』を演じ、68年に俳優座を退団、劇団四季で『ハムレット』を演じる。これは俳優座時代に千田是也の演出で経験済みだが、両者の演出や役へのアプローチの方法は全く違うもので、活気溢れる年代に刺激的だったことは容易に想像できる。
周知のごとく、浅利慶太の演出手法は日本語の発音、特に「母音」と「子音」をはっきりと区別する台詞術を徹底して訓練し、演劇界では俗に「四季式発声法」と呼ぶことがある。日本の新劇の発祥である「築地小劇場」(劇団名も劇場名も同一)の創立メンバーの一人・浅利鶴雄を父に持つ浅利慶太が、演出家としてこだわるのは、台詞をいかにわかりやすく、美しく発声するか、だ。
それまでの千田演出が台本に描かれている人物をいかにリアルに表現するかに心を砕いたものだとすれば、浅利演出はまず発音からという、いわば対極にあるという演出方法を経験したことは新鮮だったはずだ。
『ハムレット』以後、『エレクトル』、『シラノ・ド・ベルジュラック』などの作品が、浅利演出によって開花した。
この経験があったからこそ、最期まで衰えを見せなかった見事な台詞術を自分の物として生涯活かすことができたのだろう。もちろん、浅利慶太のもとを離れてもなお、自分で鍛錬し、試行錯誤を繰り返しながら磨き上げた末のことである。浅利慶太との約10年間の行動がなければ、平幹二朗の「朗誦」がこれほどに見事なものでありえたかどうか。台詞術、という点では、それほどに大きな時間だったはずだ。
ここまでの間に、千田是也のもとで「人物の理解と描写」の訓練を受け、浅利慶太と共に「台詞の発声、物の言いよう」を考えたことになる。そして蜷川幸雄との出会いがある。蜷川演出の最初は、1976年、43歳の折に演じた三島由紀夫の『近代能楽集』の一篇『卒塔婆小町』だ。これは、99歳の老婆の役で、浅利慶太との最初の作品がフランス演劇であったのに対し、蜷川幸雄との初仕事は日本の人気作家の作品だった。以降、ブレヒトの『三文オペラ』を経て、1978年には『王女メディア』を初演、以後も三度目の『ハムレット』、『近松心中物語−それは恋』、『NINAGAWA マクベス』、『元禄港歌』、『南北恋物語−人はいとしや』、『タンゴ、冬の終わりに』、『オイディプス王』と蜷川演出の舞台は続く。この中では『王女メディア』、『近松心中物語−それは恋』、『タンゴ、冬の終わりに』の三本が白眉だったと感じている。
蜷川とのコンビで仕事をしている間に、他の演出家で舞台を演じなかったわけではない。例えば東宝への客演で『狐狸狐狸ばなし』、新派への客演で『鶴八鶴次郎』など、いずれも日本の演劇史に残る名作を演じている。ただ、森繁久彌・山田五十鈴・益田喜頓など、手練れの東宝の役者に囲まれた『狐狸狐狸ばなし』などは、その個性を自由に発揮していたとはいいがたい。つまり、平幹二朗は脇で巧みな芝居を見せる人ではなく、舞台中央で輝きを放つタイプの役者なのだ。
大劇場演劇で、そうした役をいかに見せるか、に心を砕いたのが蜷川幸雄の演出ではなかっただろうか。中には、奇を衒い過ぎて評価できない作品もある。しかし、常に観客の「度肝を抜く」ような演出方法を提示し、その中に作品の世界を創るのが「蜷川流」だったように見て取れる。
どの演出家が創る芝居が好きか、というのは観客の好みに委ねるしかない。しかし、前述の三人をはじめ、多くの演出家と仕事をして来た平幹二朗は、他の名優と呼ばれる役者がそうであるように、「自分で自分を演出できる」客観性も備えていたことは事実だ。それが、後年、自らが演じたい役を、演劇鑑賞会を中心に上演して廻る作品に昇華し、これが「幹の会」の公演となった。この公演の中では自らも「演出」の任にも当たっている。これは、流れを追って考えれば何も不思議なことではなく、ごく自然にたどり着くべき場所だったのだ。それは、三人の演出家との「邂逅」を経たからこそ、行き着いた場所だったのだろう。

 演劇評論家 中村 義裕
演劇評論家 中村 義裕
目次
【出会い】
【『近松心中物語』のこと】
【平幹二朗の魅力−台詞】
【平幹二朗の魅力―愛称】
【平幹二朗の魅力-風格】
【平幹二朗の魅了-空間】
【三人の演出家】
【平幹二朗と「幹の会」】
【想い出の舞台】